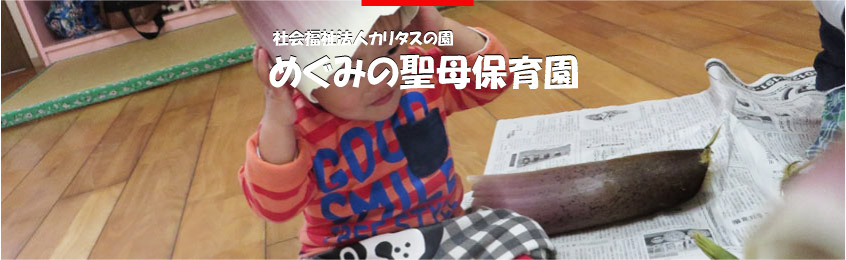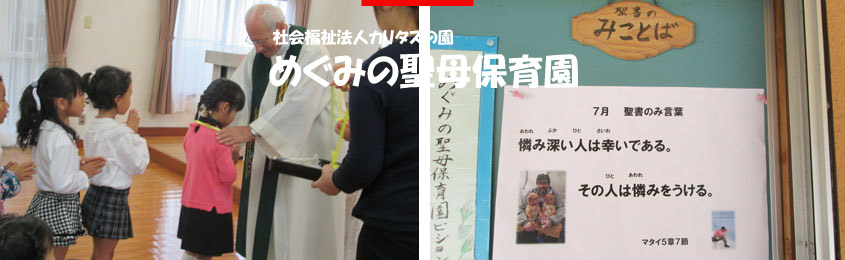心の教育
●宗教観毎日の保育の中でお祈り、讃美歌、神様の話を通して、神様の存在・偉大さ・創られたすべての物に感謝の
心を育み、人として生きて行くために必要な倫理教育、人を大切にする宗教的情操教育を大切にしています。
ドン・ボスコ教育法について
-
ドンボスコ教育法は、19世紀にイタリアのトリノで活躍した「聖ヨハネ・ボスコ」神父が提唱したものです。近代化の波に乗って巨大化していく工業都市の中で、置き去りにされていく子どもたちを助け、彼らが健全に成長(りっぱな社会人となる)出来るようになることを目標に、当時としては斬新的な彼独特の方法で、教育し、現代の教育法の先駆けの1つとなっています。
- 特徴として
- (共にいる)常に子ども達の傍にいて、その子に合った必要な援助を与え、子どもをよく知り、理解し、共感し、信頼関係を結びます。
- (個を大切にする)神様の創られるものは何ひとつ同じものはなく、成長をしっかり見分け、命の尊さについて、かけがえのない存在として大切にできるよう生活の中で、体験的に指導します。
- (愛するだけでなく子どもが愛されていると実感できる愛情の示し方)
- 子どもが理解し納得できるような愛情表現を一人ずつに与える努力をします。
- (善を選ぶ)日頃の保育の中で、良いものを選ぶこと、自ら選んで善を行い心のよろこび(成長)となる事を学べるようにします。
- 日常生活の練習=自由の獲得
- 目的: 運動の教育
- ≪自立心≫(自分の意思通りに動く体を作る)
- ≪調整≫(自分の意思をコントロールできる自分になる)
- ≪管理≫(自分の身の回りの調整・管理が出来る自分になる)
- 感覚教育
- 目的: 感覚(見る・聴く・味わう・匂う・触る)の形成期である幼児期に感覚器官を敏感に成長させると同時に、それらを整理し、秩序づけ、組織化させる、つまり知的な思考活動に先行する内容として必要な≪物の大きさ・量・粗さ・重さ・強さ・熱さ≫などを知覚させること
- :知的教育への出発点となる具体物を通してそれを抽象化(概念化)する=新たな秩序の発見につながる
- 知的教育分野
- 目的: 具体的な世界を概念化(頭の中で体験を整理し、秩序つけ、組織化する)ことで、見えない世界(抽象的な世界)でも思うように活動できるようになっていく
- 1. 文化教育:「内面のひらめき」ともいえる新しい秩序を獲得し、外へと大きく開かれる(外の世界に興味を持ち、さらに大きな様々な事象へと発展させる)
- 2. 算数教育:感覚教育から数の概念が生まれる(教具によって具体化された数)
- 3. 言語教育:感覚教育から抽象的な言葉の概念が生まれる(豊かな表現力)
- 目的: 運動の教育
モンテッソーリ教育
モンテッソーリ教育は、イタリアの精神科医・教育者であったマリア・モンテッソーリという(女医)が自分の体験を基に提唱したものです。子どもの「成長したい今」(心の欲求)に合わせた適切な教材(教具)を与える事で、子どもが満足のいく「出来た」を体験させ、心と体と精神をバランスよく成長させることのできるものです。
野菜の栽培
各クラスで野菜を育て、季節の野菜を収穫します。



中期(6年間)の目標
● お互いを信頼しあう中で、家庭的な雰囲気をつくりだす。
● ドン・ボスコの精神を深く学び実践していく。
● 子供たちが、生命の尊さを知り、優しい心を持った子供に成長する。
● 親との信頼関係を築き、子育て支援を行う。
● 全ての人に安心感を与え、地域に信頼され愛される保育園(何でも相談できる雰囲気をつくる)になる。