- 家庭のきずな
-

2011年の東日本大震災、1995年の阪神・淡路大震災以降、いやそれ以前も以降も日本人の誰もが、“きずな”という言葉の重みを感じています。それを考えずににこの言葉を聞いたなら、「時代遅れ」とか「そういうのは熱血ドラマの世界の話」などと簡単に片づけられていたかもしれません。あの未曾有の被害をもたらした大震災以来、“つながり”、“きずな”という言葉が、あちらこちらで聞こえているように思います。
大震災の数日後、あるリポーターが避難所にいる人々に聞いていました。「今、何を一番必要としていますか?」。家も車もすべてを流されてしまったであろう男性が「こうなったらもう愛だけだね。互いを思いやる心だよ」と、輪になっていた自分の家族を見まわしながら答えたその言葉が、いつまでも心に焼き付いています。毎日の報道を追いながら、次第に確信していったことがあります。悲しみや苦しみは人々を結び、きずなを深める。この限りない悲惨な状況を、マスメディアを通して見つめている地球上の津々浦々の人々が、日本に思いをはせ、連帯してくれています。そのきずなの強さ、温かさに、被災者たちはどれほど救われていることでしょう。
ホームページを担当することになって以来、この「家庭のきずな」というコーナーを設けることは、かねてからの願いでした。大震災後、きずなの大切さが見直されてきてはいるものの、誰ともつながりを見出せない“無縁社会”という言葉がまだまだクローズアップされている現代社会。このコーナーを訪れてくださる方々が、きずな、特に家庭におけるきずなについて考えたり、感じ取ったりしてくださることを願っています。そして、形は異なっていても それぞれが抱えている問題を、希望をもって乗り越えることができる小さなきっかけとなれればと祈りつつ、様々なメッセージを発信していきたいと思います。
キリスト教では、イエス・キリストが死とその苦しみを通っていのちに至ったことを記念する“復活節”があります。キリストの死は、残された弟子たちのきずなを強め、聖霊降臨の日に受けた聖霊は、弟子たちに勇気と力を与え、教会を誕生させました。2000年以上にもおよぶカトリック教会の歴史を振り返ってみても、迫害、殉教によって流された尊い血は信徒のきずなを強め、教会の土台を固め、発展させていきました。 死は命の終わりではなく、永遠の命の始まりであること、無からすべてを創られる神を信じる者として、被災者の方々が、地震による悲惨な状況を希望と支援のきずなによって乗り越え、再び立ちあがることができることを祈り続けていきたいと思います。 - 家族の絆について考える
-
飯島裕子
3.11の東日本大震災で、あらためて“家族の絆”について考えたという人が少なくないだろう。
「震災後、家族の無事は確認できたし、少し待てば電車が動くこともわかっていたけれど、それでも会社から郊外にある自宅まで7時間かけて歩いたんです。地震で自分にとって一番大切なものは家族なんだってつくづく感じて・・・・・・居ても立っても居られなくなったんですよ」
最近、取材で出会った30代のビジネスマンは当時のことをこう振り返った。これまで外資系金融会社を何社も渡り歩き、大きな成功を収めてきた一方、家族と過ごす時間を犠牲にすることも多かったという。彼は今、収入が下がったとしても、家族との時間を多く取れる仕事への転職を考えている。
彼同様、震災後、家族観や仕事観が変化したという人は少なくない。働き盛りのビジネスマンを対象にしたあるアンケートでは、震災後「家族との時間が増えた」と答えた人の数が約7割を超えている。震災は日本人がもっていたさまざまな価値観に揺さぶりをかけ、結果として家族の絆を深めたということができるだろう。
いざという時、真価が問われる家族の絆。いつもは見えないけれど、確かに存在する絆だからこそ、必要な時、強く結び直すことができるのだ。
一方、完全に切れてしまい、どんなに結び目を繋いでも修復できない絆もある。私は、20代、30代の若さでホームレス状態にある人を取材してきたが、彼らの大半は、家族との絆を完全に失ってしまっている。その若さなら、家族、親戚など誰かしら頼れる人が生きているのではないか? 実家に帰ればいいのではないか? と思われるかもしれない。
しかし、養護施設で育ったため、頼れる家族がいない、両親が幼いころ離婚し、それぞれ別の家族をもったため、帰れる実家がない、家族も生活に困窮しており、戻る場所がない、父親の暴力から逃れ、家を出たため、帰れない、母一人子一人として育ち、母親が亡くなったため、20代で天涯孤独になってしまった・・・・・・など、彼らはさまざまな理由から家族の絆を断たれてしまっている。自分から家族の絆を断ったというより、そもそも絆と呼べるもの自体存在していなかったり、さまざまな理由で絆が断裂してしまっているのだ。
若いホームレスたちの置かれている状況は、決して遠い話ではない。少子高齢化で地縁、血縁、社縁といったさまざまな縁が切れていく“無縁社会”が身近なものになっていることはさまざまなメディアで報じられているとおりだ。
家族の絆が欠かせない大切なモノであるということは、十分すぎるほどわかっている。しかし完全に切れてしまっている家族の絆をどう紡ぎ直せばいいのか?
明確な答えはわからないが、家族の絆の“家族”の定義をもう少し広げてみてはどうだろうかと考える。そしてそんな時、私が連想するのは、修道生活を送る修道女や司祭、修道者であり、さらには教会コミュニティの存在だ。血縁でも地縁でもない、信仰という縁で結ばれた“家族”として、千年以上にわたって存在し続けてきた修道会や教会は“無縁社会”に立ち向かう、一つのヒントになるのではないだろうか。
震災後、人と人の絆が重視され、さまざまな“縁”を紡ぎ直そうとする動きが、各地で起こり始めている。国籍も貧富も年齢も関係ない、イエス・キリストを中心に据えた“家族の絆”の真価を問われる時ではないかと考える。
 プロフィール
プロフィール
飯島裕子=ノンフィクションライター。
著書に『ルポ若者ホームレス』(ちくま新書)、インタビュー集に『99人の小さな転機のつくり方』(ビッグイシュー編集部編、大和書房)がある。
井荻聖母幼稚園卒園。 - きずなは愛
-
シスターアグリッピナ頭島富美枝
“おばあちゃん、ミエだけど、いまから会いにいってもいい?”
“ミエちゃんね、いま何処におると?”
“おばあちゃん家のそばだよ”
“ミエちゃんがひとりねー”
“ううん、お友達も一緒にいると”
“なんば遠慮するとね、はようおいで、待っとるけんね”
“わかった、いまからすぐにいくね”
ミエが5歳で弟が3歳の時、海で真面目に働く父親のもとから、他の男と一緒になるため母親は出て行った。それ以来ミエと弟は、祖母と叔母家族のもとで暮らしていた。
ところが、ミエが高校2年の夏、突然、“お母さんと一緒に暮らしたい”と言い出した。祖母は弟にも気を遣って“一緒に行きたければ行ってもいいのよ”と声をかけた。しかし、弟は“俺はいかん、お姉ちゃんはバカだ”と言って怒りを表した。弟の怒りには、母親を慕う気持ちをかみ殺して今まで耐えてきた“男の子としての思い”が込められていた。
そんな弟の生活にもやがて異常が生じるようになり、心配した祖母は父親と相談した結果、弟が中学に進学する前に信頼できる人に全てを話せる場を設けた。そこで彼は一つの山を越えたのである。一方のミエも、実母の家庭で暮らしながら18歳となり、家庭はどうあるべきかを少しは考えたのであろう。2年という月日が過ぎての祖母への電話であった。
上記のエピソードは、あって欲しくはないものの、“無縁社会”などと呼ばれる現代社会においては、起こり得るエピソードである。皆、幸せになりたい、人を幸せにしたい、という思いは持っているはずなのに、皆、精一杯生きているはずなのに、思いも寄らないところで破綻が生じたり、誰が悪いとも言えない現実が起こったりすることもあり、そこに人間の持つ弱さが重なり合って悲しい結果となることもある。その中で弱い者、小さい者たちが傷つき、倒れそうになる。しかし、そういう弱く悲しい人間模様の中でも、神の神秘が現れているように思うときがある。弱い者、小さい者こそが大切にされ、周りの人々に支えられ助けられながら立ち上がろうとするとき、互いを思いやりながら生きるときである。
世界中の人々の目が、そして心が、日本へと注がれた東日本大震災の大惨事の時もそうであった。家も物も愛する者をも失い、弱い立場に立たされた人々を心から思い、支え、助けようとした人々は多く、それは今でもいろいろな形で広がりを見せている。人と人とのきずなの中に神が確かに存在し、そこに深い愛と感動が存在し、大きな力となって人間の弱さを支えてくれているように思う。小さな愛の応答、愛の行為の積み重ねが、大きな力となってつながっていくのである。
今、「家庭のきずな」を考えるとき、現代社会がおろそかにし、忘れられてきた、ごく当たり前の家庭のあり方を実践することが大切なのではないかと思う。子どもたちは親たちに心配をかけつつも親のためにと贅沢を望まないで生きる。親たちはつらくとも子どものために働き、ご飯を炊いて、美味しい物を作って家族で食べる。そしてお互いのことを思いやりながら生きる。そういうごく当たり前の家庭が少なくなっているように思うのである。両親は共稼ぎ、子どもたちは部活もしくは塾通い、食事を共にするどころか、親も子も疲れ果てて一言も交わさない日も少なくない現代にあっては、当たり前の家庭を見つけるのは難しいことなのかもしれない。しかし、そのような当たり前の繰り返しこそが、目に見えない親子のきずなを作っていくし、子どもたち自身もそういう雰囲気の中でこそ、一番落ちつける場所を見つけ、たとえつらいことが起きたとしてもそれを乗り越えながら成長していけるのではないだろうか。そしてこのように繰り返される家庭のきずなこそ、最も深いきずなと呼べるのではないだろうか。
小さな者、弱い者、困っている者に目を向けず、自分のやりたいことをし、所有したいもの所有し、自分だけの自由を満たすことのみを追求し続ければ、家庭のきずなは次第に薄れていく。そこには互いを結ぶ愛がないからである。きずなは思いやりであり、愛なのである。 - 失われないもの 与えられたもの
-
菅原裕二 S.J.
3月の東日本大震災で故郷が被災しました。ローマの修道院に居ながら、日本から送られてくる映像にくぎ付けになり、家族や友人たちのことが心配になり、遠くからでは何もできなくて歯がゆい思いをしました。夏休みに生まれ育った町に車で降り立った時、自分の感情を表現する言葉が見つからないという体験をしました。
幼少時代を過ごしたK市では津波で大叔母が亡くなりました。親戚を見舞い、洗礼を受けた教会を訪問し、母方の家の墓参りをして帰りました。少年時代を過ごしたO市には今も兄が住んでいますが、中学高校時代に住んでいた家は二軒とも流され、父方の祖父母が眠っていた教会の納骨堂は跡形もなく壊されていました。
両親が開いていた店は駅前の商店街にありましたが、線路も駅舎もなくなってしまい、ホームに立つと見覚えのない山や道が並んでいました。たしかに私を育ててくれた町なのですが、私が覚えているのとは異なる街並みが目の前にありました。最初に受けたショックは、恐ろしさではなく喪失感であることに少しずつ気がついていきました。<
故郷を訪ねたことで、その後も子供の頃の出来事や家族のことを考える機会が増えました。同じ被災地なのに、隣町の惨状を見たときにはかわいそうだ、苦しかっただろうなという気持ちが起こったものの喪失感はありませんでした。壊れてしまったのが自分の見知っている町だと、同じ光景は異なる意味を持ち始めます。その町は自分が選んで生まれた訳ではないのに特別な意味を持っています。だれか他の人によって準備され、与えられたものであるのに自分の大切な一部になっているのです。
考えてみれば、私の人生は自分が選んだものではありません。私は生まれる場所も、生まれる時も選ぶことができませんでした。生まれてくること自体、選ぶことができる対象ではなく、だれを親として、どんな兄弟を頂いて生まれてくるのか(それがないと今の自分はありえないのに)実は全部与えられたものです。
厳しい言い方をすれば、親は私が生まれてくることを望んだのではなく、もう一人男の子か女の子がほしかったので、私が私として生まれることを望んだのは神さまです。「あなたはわたしの内臓を造り、母の胎内にわたしを組み立ててくださった」(詩編139編13節)と歌われている通りです。
子供は親を選ぶことができませんし、親もまた子供を選ぶことができません。しかし、私は偶然の産物ではなく、神さまが望んで生まれた子供、神に創られた大切な人間です。神の子イエスが生まれるときのために、神は母マリアを生まれたときから汚れのない者として準備なさったとカトリック教会は信じ、宣言しています(無原罪の御宿り)。
イエスに起こったことは私にも起こるかもしれません。親や兄弟や故郷の町は、私が私として生まれることをどれだけ望んでいたのか、そのことに明確な答えはないのですが、神さまはきっと私の父や母を、私のために一番良いものとしてお造りになり、準備し、私があの町で生まれることを望まれたのだろうと思います。
この神さまのことを教えてくれたのはキリスト者である両親です。私が父と母から受けた賜物は第一に命ですが、第二には信仰です。信仰を保ち、育て深める努力は毎日しているつもりですが、信じる内容も祈りの仕方も私が他の人を通して受け取ったものです。受け取る人の第一の務めは感謝することだろうと思います。それは与えてくれた方が誰であるかを知ることから始まります。
人生は受け取ることの連続で、人は受け取ることを通して人になっていくのだろうと思います。きちんと受け止め、深めていくことが、私が生きていることの意味であり、使命だろうと思います。受け取ったものを深め、生かすと、神は「忠実な良い僕だ、よくやった」と喜んでくださる(マタイ25章21節)と聖書は教えています。
故郷は大きな被害を受け、失ったものもたくさんあるのですが、信仰や親から受けた恩、友人たちの友情など、私の人生には失われ得ないものもたくさんあるのだと気がついた旅でもありました。プロフィール
菅原 裕二 師
イエズス会司祭
・教皇庁立グレゴリアン大学 教会法学部教授
Pontifica Universita Gregoriana - 生命を育む場、家庭
-
シスターエミリアナ朴潤淑
韓国の元旦、特に陰暦の1月1日には、朝早く家族全員が一緒に集まって祖先のことを思い出して祭祀を行ない、家族の目上の人たちに丁寧にあいさつのお辞儀をします。両親のもとから遠く離れて住んでいる子どもたちも、この日ばかりは皆故郷に帰って家族全員が一つに集まって祭祀を行なうことで家族の絆を固め、また1年を元気に生きていくための慰めと力を得るのである。‘家庭’は、一人の人間が神から生命を与えられて再び神のもとに帰るまで、この世界に生きている間、喜びも悲しみも共に分かち合う住まいだからである。
私は、カトリック信者の家庭に生まれ、教会の庭で飛び跳ねて遊びながら育ちました。私の家族が通っていた教会の庭の入口には、幼子イエス様を抱いた大きな聖母像がありましたが、私の家の居間に置かれている小さな銅像は、幼子イエス様を抱いているのは聖母ではなく男性の姿をしていました。ですから、この方がどなたなのか気になった私がある日母親に尋ねると、母親はこのように答えました。
“この方はイエス様を育ててくださった養父の聖ヨゼフ様ですよ。マリア様が、神の子であるイエス様をお産みになったお母さんだということは知っているでしょう? ヨゼフ様は、そのイエス様がすくすくとよく育つように見守り育てて下さった方だから、この方をイエス様の養父と言うのよ。あなたもイエス様のようにもともとは神様の娘で、お父さんとお母さんは神様からお願いされて、あなたを生んで育てているのよ。だから、おまえに生命を与えて下さった本当のお父さんは神様ですよ。”
今考えて見ると、その時こそ私が神様の存在と私の存在の根源を具体的に初めて教えられた瞬間であったと思います。まだ小学校に通う前の、幼なかった私は、その言葉をそのまま受け入れました。そして、その時のことは今も生き生きと記憶に残っています。その後、日曜学校で、シスターや先生から教理を習い、もっと大きくなってからは進んで聖書も読むようになって、いろいろと知識も増えて行きましたが、今でも私の心に残っているのは幼い頃に家庭で聞いたこれらの話です。天地創造の話、ノアの洪水の話、ロトの妻が塩の柱になってしまった話、サムソンの話等、おもしろくて不思議な聖書の話を聞くと、私はそれを友だちにそのまま話してあげたりしました。 “みんな聞いて。私のお母さんの話では、私の本当のお父さんは神様だって。私のお父さんとお母さんは、神様からお願いされて私を育てているんだって…” “みんな、虹がどうして出来たか知ってる? 虹は、昔々、ノアというとても善良なおじいさんが住んでいて… “
私の経験を通して考えて見ると、家庭とは “神様の生命を生み育てる揺りかごであり、人間が自分の存在の根源を悟り、信じて幸せに生きて行くことのできる信仰を教える学校”だと言えると思います。家庭が人間社会の核細胞であるだけでなく、教会の核細胞であると称するのもまさにこのような理由からではないでしょうか。 ところで、私たち修道者は、自分が生まれて育った家庭を離れると同時に、結婚して新しい家庭を作ることも放棄しました。“人の子には枕する所もない”(マタイ8,20; ルカ9,58)と言われたイエス様のように、“神の御心を行なう人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母”(マルコ3,35)という新しい家族を形成したからです。
教皇ヨハネ・パウロ2世は、使徒的勧告<家庭>で仰っています。 “修道者としてまたは、信徒として生涯を教会にささげた人々が家庭の使徒職に対してなしうる奉仕の第一の根本的かつ独自のことは、とりもなおさず神への献身にあります。… 修道者は…家庭の司牧を最優先の任務の一つとして、現代世界の状況のためにより切実になった任務を完遂することを切に追及するのです。“(74項参照)
私たちの会憲29条では、‘家庭がキリストを中心とし、生命の大切さについての深い認識をもつことによって、福音の光を輝かせる信仰の揺りかごの役割を果たすことができるよう’助けることを勧めています。
今日の家庭の現実は暗く感じられます。ある本で読んだ韓国社会の現実ですが、他の国の状況も大きくは変わらないと思います。
“大部分の父親は、朝早く職場に出勤し夜は遅く帰宅するので家庭に関心をもつ時間がなく、母親は、共稼ぎ、あるいは趣味生活、社会生活という理由で家庭にいる時間がなく、子どもたちは、入試本位の教育のために学校での勉強だけでなく課外の勉強までしなければならないため帰宅が遅くなり時間がない。家族が一緒に集まっていても、テレビやコンピューター等の電子機器類が家族の目と耳を奪ってしまう。その結果、家庭での祈りや対話がなくなり、私たちの家庭は、‘下宿’ または、‘旅館’のようになってしまった。”
従って私たちは、可哀そうで悲惨な家庭により一層関心を持って、全世界の家庭が家庭本来の姿を具現できるよう奉仕するために、私たちのカリスマに沿った使徒職の方法を見出さなければならず、その一環として2012年6月には、修道会次元での “家庭の使徒職研究会”を開催する予定です。
ある人が、家庭生活は ‘うまずたゆまず明け渡していく生活’であると言っています。ですから、自分よりも家族をより配慮し、家族のために自分を明け渡すことによって幸せを感じるような生き方をしなければならず、それが困難になると家庭の幸せも壊れてしまうのだと思います。“自己を明け渡す旅”であるという点が、家庭生活と修道生活の共通点であり、全ての人間は、それぞれ神様から呼ばれた姿でお互いに助けとなれる存在であるということを悟りました。
新しい年、新しい日が、明けました。
この1年も全世界の家庭に、神様の祝福が豊かにそそがれる年となりますように。
Sr. Emiliana 朴潤淑(イエスのカリタス修道女会総長)

- きずなの検証(日々の検証)
-
堤 澄子
 毎月掲載される「家庭のきずな」のコーナーに、被災地からどんなメッセージを届けられるかずっと考えていました。私は東日本大震災で被災地に入り、心のケアのための支援活動をしています。私たちが行うのは医療的アプローチとしてではなく、心と魂、霊的ケアとしてのスピリチュアルケアという側面からのアプローチです。(キリスト教ではパストラルケアと呼んでいます。)人間は人生の中で、薬では治らない、検査をしてもわからない、レントゲンにも写らない、手術しても取り除くことができない痛み・苦しみ・さけびを体験するときがあります。それは人間の存在それ自体から、いのちの根源から沸き起こってくる「いのちのさけび・魂のさけび」です。このような場合には、治すための治療ではなく、いやしのためのケアが必要になります。被災地では地震と津波で町まるごと流され、家も財産も仕事も失い、大切な家族、友だち、同僚など多くのいのちを失いました。どこに行っても「いのちのさけび・魂のさけび」であふれていました。ほぼ1年、被災地にとどまり、ひたすらそのさけびに耳を傾け、痛むいのちに寄り添い、彼らとともに生きてきました。その中で「家庭のきずな」という視点から感じたことを分かち合いたいと思います。まず「家庭のきずな」を確かなものとしていくために、日頃からの「きずなの検証(日々の検証)」が大切だと感じています。言い換えれば「人間関係とコミュニケーションの検証」と言えるでしょう。
毎月掲載される「家庭のきずな」のコーナーに、被災地からどんなメッセージを届けられるかずっと考えていました。私は東日本大震災で被災地に入り、心のケアのための支援活動をしています。私たちが行うのは医療的アプローチとしてではなく、心と魂、霊的ケアとしてのスピリチュアルケアという側面からのアプローチです。(キリスト教ではパストラルケアと呼んでいます。)人間は人生の中で、薬では治らない、検査をしてもわからない、レントゲンにも写らない、手術しても取り除くことができない痛み・苦しみ・さけびを体験するときがあります。それは人間の存在それ自体から、いのちの根源から沸き起こってくる「いのちのさけび・魂のさけび」です。このような場合には、治すための治療ではなく、いやしのためのケアが必要になります。被災地では地震と津波で町まるごと流され、家も財産も仕事も失い、大切な家族、友だち、同僚など多くのいのちを失いました。どこに行っても「いのちのさけび・魂のさけび」であふれていました。ほぼ1年、被災地にとどまり、ひたすらそのさけびに耳を傾け、痛むいのちに寄り添い、彼らとともに生きてきました。その中で「家庭のきずな」という視点から感じたことを分かち合いたいと思います。まず「家庭のきずな」を確かなものとしていくために、日頃からの「きずなの検証(日々の検証)」が大切だと感じています。言い換えれば「人間関係とコミュニケーションの検証」と言えるでしょう。
「人格と人格の出会い」につながる人間関係とコミュニケーション
今回の震災によって、家族のきずながより硬くなった家族もいれば、もろさが露呈され崩壊する家族もありました。錯覚、勘違い、思い込みの中でいがみ合い、ののしり合う場面もありました。苦しい時だからこそ支え合わなければならないのに互いにキズつけあってしまう悲しい光景も見られました。確かに極限状態に置かれストレスにさらされ、普通の精神状態ではないということも理解しています。
それでも、対処する術、改善する方法はあると思うのです。それを身につけていないために致命的な状況に陥っている方がとても多いと感じました。つまり「人間関係とコミュニケーション」の学習の不足です。日常的に自分の気持ちや感情、本音を他者に伝えたり言葉で表現する習慣が少なく「人格と人格の出会い」という体験もほとんどないということです。照れくささや面倒、あるいはものを言わないのが美徳という風習も根強いからかもしれません。特に女性の場合は、家庭においても地域においても地位の低さ弱さが色濃く見られ、人間として女性としての尊厳が十分保たれていないと感じられます。小さな町ゆえのあたたかさとそれ以上に生きる厳しさも受け取りました。そのような中でも共通理解として持っておきたいことは、価値観が多様化し多くの情報があふれている今の時代、内面の世界において「以心伝心」はあり得ないことです。たとえ夫婦でも親子でも全く違う存在であり別人格であり、「一個の人格を持った人間」です。その中でほんものの「家庭のきずな」を生きようとするならば、しっかりと「人格と人格の出会い」につながる人間関係とコミュニケーションを日々意識して生きることが大切だと感じます。その度合いがすなわち「きずなの検証」と言えるでしょう。そうすれば、たとえどのような危機的な状況に遭遇しても、立て直す可能があるのです。
家族の魂のさけび・・・届いていますか?
たとえば、都会では、個を大切にするというポリシーのもとに一緒に食事をしない家庭もあります。一緒に食事をしていてもいつもテレビを観ながら・・実は一言も語っていないことに気づかない家族もあります。また、ある時は数人のこどもが電車に乗ってきて・・・一斉に携帯でゲームをはじめ、友だちとひと言も話さない光景がありました。あるいは、おかあさんおとうさんにほめてもらいたくて一生懸命におりこうさん優等生を演じて疲れきって・・・本当は愛してほしいのに素直に言えない。みなさんの家庭は大丈夫でしょうか。あなたの大切な家族が、何を考え何を思い、何に悩んでいるかしっかり伝え合っていますか?家族の魂のさけび・・・届いていますか?「人格と人格の出会い」につながる人間関係とコミュニケーションを生きていますか?
HUGすることからはじめましょう。
被災地では、こころのケアはまず自分をHUGすることから、互いにHUGすることからはじめましょう。そう呼びかけ上手にHUGする練習をしています。みんな無条件で大事な存在だということ。自分の存在にOKすること。あったかいHUGがあれば自然と言葉も素直にでてきて気持ちも楽になるようです。大人もこどもも、男性も女性も、おじいちゃんもおばあちゃんも、みんなHUGが大好きです。HUGしてほしいのです。ひとつひとつの家庭がまごころからのHUG、いのちのHUGで満たされて「家庭のきずな」を育てていくことができますように。 (HUGハグは愛情をもって抱きしめるという意味) - 俺たち、人間なんだもん!
-
道向初幸
「はつ!そげん悪かことばっかしよったら母ちゃんにゆうけんね」
「おばちゃん、言わんで。おこらるったい」
 学校が終わると散々道草を楽しみ、家に着くや否や、母が出かけていることをいいことに風呂敷風ランドセルを土間に投げ捨て、近くに住んでいるしーか(友人である静香のあだ名)のうちで日が暮れるまで遊んだ。そんな風景の中で時折飛び出す(しーかの)おばちゃんの声。悪ガキだった自分を叱っているのが、母ではなくおばちゃんであるところが妙におかしくも、忘れかけていたふれあいの心地よさが懐かしくよみがえってくる。
学校が終わると散々道草を楽しみ、家に着くや否や、母が出かけていることをいいことに風呂敷風ランドセルを土間に投げ捨て、近くに住んでいるしーか(友人である静香のあだ名)のうちで日が暮れるまで遊んだ。そんな風景の中で時折飛び出す(しーかの)おばちゃんの声。悪ガキだった自分を叱っているのが、母ではなくおばちゃんであるところが妙におかしくも、忘れかけていたふれあいの心地よさが懐かしくよみがえってくる。
小さな集落の中では、子どもたちにとって、それぞれの家が我が家でもあった。玄関の鍵などなく、座敷も納戸も意味をなさず、所構わずもぐりこんでかくれんぼ。馬乗りにも興じた。おなかがすけばおばちゃんがふかしてくれたいもと焼いた鰯が目の前に用意された。
子牛が生まれると聞けば村の男衆が駆け付け、固唾をのんで見守った。誰かが病気だと分かれば入れ替わり立ち替わり皆が看病に行き、逝く人がいれば老いも若きも関係なく行列をなし、祈りのうちに見送った。
息がつまるほど互いのことを気にかけ、当然のことのように思いやり、肩を寄せ合って生きていた。
あれから55年かぁ。しばしいにしえの余韻に浸っていると、ホームの少年が、「おやじ!何さっきからボーっとしてため息ついてんだよ」ときた。「古き良き時代を思い出してんだよ、今時のお前には分からんだろうけどな」と埃にまみれた少年時代の一こまを語る。「何だよおやじ、それじゃぁまるで浦島太郎じゃん。俺なんかさ、酔っ払った母ちゃんに殴られ、お前なんかどっか行けって。父ちゃんなんか借金こさえて逃げて終わりだよ。おやじの話なんかありえねえよ」とここぞとばかりに思いのたけをぶつけてくる。
返す言葉が見つからない。子どもには何の責任もないのに。一人の親として釈然としないものを感じる。一度とは言わず自分の胸に抱いて何度も頬ずりしたであろうに。将来を夢見て、我が子の一つ一つに悲喜こもごもの涙を流したであろうに。それがいつしか親は子を疎み、子はそんな親から傷つき離れ、社会の闇に埋もれてゆく。越えようのない溝、交わりようのない心が人の間をすり抜け、今日も繰り返される忌まわしい事件の数々をテレビが伝えている。
人間は何か大事なものを置き忘れ、行く先を間違えているのでは、と識者たちが言い始めて久しい。それでも人は飽食を求め、いたずらに富をかき集め、足ることを知らなかった。誰もが心のどこかでこれではいけないと気付いていたはずなのに。みんなも変わらない、何で自分だけ、割りに合わないよ、という我欲のささやきに互いが自分の気付きを封じ込め、“自分さえよければ”の心と共に歩を進めた。
しかし、やるせないほどの無責任さと独りよがりに怒りと倦怠は渦巻き、人はようやく自分を取り戻しつつある。
癒し、絆。人が人に飢え、人を求め始めてようやく。そうだよ、何もなしに親が自分の子どもを疎んじるはずがない。人が人を好き好んで騙すか?友達、クラスの仲間をいじめるか?人が困っているのに知らんぷりするわけないだろ。
俺たちは人間なんだよ。
何に憂うことなく、静かな自然と温かい村という家族に包まれて生きたはつとしーかがそう叫んでいるような気がする。
そうだよ、少しだけ我慢すればいいんだよ。少しだけ譲ればいいんだよ。少しだけ分けてあげればいいんだよ。少しだけ聞いてあげればいいんだよ。少しだけ一緒にいてあげればいいんだよ。だってみんな同じ人間なんだもん。
自立援助ホーム CapeDiem (カーペ ディーエム) 理事長 道向初幸 - 私の召命の歩み ~信仰の証~
-
シスターアンナ藤原睦子
私は父と母、兄と私の4人家族で、ごく普通の家庭で育ちました。出身は岡山で、岡山南教会で幼児洗礼を受けました。父はもともとカトリックの信者で、母は結婚して信者になりました。4~5歳の頃は、花屋やケーキ屋で仕事をしたいと思っていましたが、小学生になると、いつの間にかシスターになりたいと思い始めていました。それは、私の大叔母であるSr.ヴィヴィナ大山が休暇の度に私の家へ泊まりに来ており、シスターと接するうちに心が惹かれていったからだと思います。しかし、シスターが休暇を終えて修道院へ帰られると、またいつもの生活に戻りシスターになりたいと思う気持ちはすっかり忘れていました。
ところが中学一年の夏休み中、ちょうど休暇で帰省していたシスターから「シスターにならない?」と声を掛けられ、私はすぐに「なりたい」と答えてしまい、なんと夏休み中に入会することを決め、急いで荷造りをし上京しました。父にとっては一人娘でもあるし、まだ12歳という若さで親元を離れていくことになるので初めは反対しましたが、母が説得したところ“すぐに帰ってくるだろう”と思い、承諾してくれました。それから学生志願者としてカリタス会に受け入れられ、修道院で共同生活を送りながら一般の中学、高校に通いました。親元を離れ、正直ホームシックになることもありましたが、共に志願期を過ごした仲間がいたおかげで乗り越えることができました。
高校を卒業した後は、アスピラントとして多摩修道院で2年間過ごし、そしてポストラント、修練期を過ごしていましたが、あと一年でシスターになるというところで、突然、母の病が見つかり、看病のため実家へ戻ることになりました。私は特にシスターになるのを辞めようと悩んでいたわけでもなく、いきなり社会での生活を余儀なくすることになりました。荷物をまとめながら、“母の病は本当に大丈夫なのか”と心配する半面、“私には召命がなかったのか”と落ち込むなど、複雑な思いで修道院を後にしました。
すぐに病院へ向かったのですが、医師の話によると、母は急性の脳腫瘍の癌で、脳幹という難しいところに腫瘍があり、手術をしても全部は摘出することはできないとはっきり言われました。病室にいる母はいつも明るく、あんなに元気に話したり、笑ったりしている母が末期の癌だとは、本当に信じられませんでした。時には、頭が痛くて辛そうにしていることもありましたが、母の周りには常にお見舞いに来て下さった方々がいて、多くの方々の温かい心遣いに、毎日感謝していました。そして、手術をするまでの期間、久しぶりに家族4人がそろって過ごすことができたことは、本当に大きな恵みであったと思います。母はよく、「私の夢には、なぜか神父様やシスターの夢しか出てこん」と言っていました。それだけカリタス会のシスター方が心を込めて祈って下さっていたからだと思います。母の病気快復のため、また看病をしている私や家族を気遣い、心配して励ましのお便りを書いて下さった方々、また電話や直接お見舞いに来て下さったシスター方には本当に感謝しています。
母は、手術前に病者の塗油を受けることができ、ご聖体を頂いた後、静かに目を閉じ、典礼聖歌の[わたしたちは魚のよう 神様の愛のなかで泳ぐ]を口ずさみながら、涙を流して神様に感謝していました。そして「もう悔いはありません。み旨のままに…。」と祈りを捧げていました。そんな母を見て、私はただただ自分が恥ずかしくなりました。修練の途中だった私より、ずっと母の方が修道者のようで、全てを感謝して神に委ねている母の信仰は“本物だ”と思いました。手術の時間が近づくと、病室から一緒に手をつないで歩いて行き、一人で元気に手を振りながら手術室に入って行った母は、手術後、意識不明の重体になり、55歳という若さで天に召されました。
病院を後にする時、ある看護師から声を掛けられ、「シスター頑張ってね」と言われました。その時、私は私服を着ていましたし、修道院へ行っていたことも話したことがなかったので、どうして知っているのかを尋ねたところ、母が入院していた時に、「私が一番嬉しいのは娘がシスターになること」と話していたそうです。これを聞いた時、“私が信じた道は間違っていなかった。“私が進む道はこれだ”と、強く思いました。今思えば、これは母の遺言でもあり、シスターにならざるを得なくなったきっかけとも言えます。しかし、この確信があったからこそ、シスターになりたいと思う気持ちが変わらぬまま、約3年間過ごすことができたと思うので感謝しています。
無事にお通夜や葬儀を終え、私たち家族3人はぐっと力が抜けてしまいました。母が亡くなってしばらくの間、深い悲しみと絶望の中にあった時、私は教会へ行ってご聖体の前で心の思いを打ち明けることで、少しずつ癒されていきました。気付けば、私の周りには沢山の人がいて、母に代って愛情を注ぎ、私や家族のために祈って下さる方、そしてカリタス会のシスターから沢山の手紙が届いたり、電話をかけて下さったり、岡山まで会いに来て下さるなど、神様がそのように計らって下さったおかげで慰められ、神様は絶えず私のことを心にかけ、人を遣わして支えて下さっていたのだと強く感じました。時には困難にぶつかることもありましたが、家族や親戚、恩人、友人から沢山の愛を受けた分、私は心から神と人とに仕えていきたいと感じるようになりました。
しかし、私の父は昔から糖尿病で週3回の透析をしており、父の看病や家事など、母がしていたことを私がすることになり、とても修道院へ戻れる状態ではありませんでした。しかし、何もしないで家にいるだけではもったいないと考え、若いうちに何か資格を取りたいと思い、父に相談して短大で2年間、幼児教育を学びました。そして卒業が近づいた頃、私は父と兄をおいて行くわけにはいかないと思い、岡山で就職をすることを考えていましたが、父に「シスターになりたいと思う気持ちは変わっていないのか?」と言われ、私は「変わってないよ」と答えたら、「シスターになりたいと思う気持ちがあるうちに帰りなさい。何も心配することはない。なるようにしかならないんだから…。」と言って背中を押してくれました。「自分の人生なのだから、後悔をしないように好きなように生きていきなさい」といつも私を励ましてくれた父に感謝しています。そして、本当は傍にいて家事や看病をしてほしいと思っているのに、私の思いを理解し、応援してくれた兄に感謝しています。また、自分の娘のように思い、尽くしてくれた親戚や、妹のように可愛がってくれた恩人、傍で支えてくれた友人に心から感謝しています。
それから思い切って修道院へ戻り、2010年12月8日に初誓願を宣立する恵みを頂きました。神様のご計画は本当に分からないものですが、これまでのことを振り返った時、この様々な体験があって今の私があり、神様の恵みによって修道者として生きていく道に招かれたことを感謝しています。結婚生活に招かれた人もいれば、修道生活に招かれた人もいます。神様は一人ひとりに合った、そしてその人らしく生きていくことのできる生き方を準備して下さっているのだと思います。ある神父様に「シスターになることより、シスターとして死ぬことの方が難しいよ」と言われたことがあります。どのように生き、証していくのかは、これからの課題でもあります。私は、いつも人との出会いや体験を通して、神様の方へと心が開かれていきました。だから私も、修道者としてキリストの手足となって、一人でも多くの人を神様の方へ導く使命が与えられているのだと感じています。一人ひとりは神様にとってかけがえのない大切な存在であり、無条件に愛されていることをしっかり伝えていきたいと思います。この先、どのような人生を歩んでいくのか分かりませんが、必要な時に必要な恵みを与えて下さる神様に信頼して、これからの人生を喜んで愛のうちに歩んでいきたいと思っております。ありがとうございました。 - 帰る場所
-
田中重治 (福岡教区司祭)
 「ただいま」「お帰り」。子どもの時から交わし続けた何気ない帰宅の挨拶。しかし、この「挨拶」というものは相手があってはじめて出来るもの。まして「帰宅」の挨拶は、帰る場所があって、迎えてくれる人がいてはじめて出来るものです。よく、一人暮らしを始めた若者たちが、最初は楽しくって仕方のない生活だったのに、次第に、誰も「お帰り」を言ってくれない、待っている人のいない部屋に帰るのが苦痛に、寂しさになっていきます。
「ただいま」「お帰り」。子どもの時から交わし続けた何気ない帰宅の挨拶。しかし、この「挨拶」というものは相手があってはじめて出来るもの。まして「帰宅」の挨拶は、帰る場所があって、迎えてくれる人がいてはじめて出来るものです。よく、一人暮らしを始めた若者たちが、最初は楽しくって仕方のない生活だったのに、次第に、誰も「お帰り」を言ってくれない、待っている人のいない部屋に帰るのが苦痛に、寂しさになっていきます。
考えてみると、司祭を志して神学校に入りましたが、神学校ではこの帰宅の挨拶はありませんでした。休暇で実家に帰ると、家族がお帰りと言ってくれましたが、日常では交わさなくなった挨拶。そこに一緒に暮らしているというのに、お互いに帰宅の挨拶は交わさなかったように思います。そこが、本来の「帰る場所」ではなく、ただ「一時的に住んでいる場所」ということでしょうか。
動物に帰巣本能があり、わたしたち人間には帰るべき場所を求める心が与えられています。「家族」です。私たち司祭は、確かに特定の家族を持ちません。それは、どこにでも赴任して、そこを居場所とすることができるためだとも言われたりします。確かに、赴任先には数年間の滞在で、また次の教会へ。そして暗黙の了解として、前任地とのかかわりを抑えていく、新任者のために。そんな私ですから、ぽーんとローマにも来ることが出来たのでしょう。
イタリアに来て、私はここは一時的な滞在場所で、帰るべき場所は「日本」だと強く意識しました。期間の決まった留学ですから当然です。しかし、イタリアの勉強のために最初に数ヶ月お世話になった小教区からローマに移る時、そこの主任神父様から言われました。「さようなら」じゃなく、「ローマに行ってきます」と言えと。ここはお前の帰るべき場所だからと。とてもうれしく感じました。実際、この3年間、ほぼ休暇のたびにこの小教区でお世話になりましたが、その都度、「ただいま」「お帰り」「行ってきます」の挨拶を交わしてきました。私の支えでした。ここがイタリアでの帰る場所なんだって。
日本の青年たちからも度々メールをいただきました。「神父様の帰りを待っています。神父様の帰るべき場所はわたしたちのところです」と。うれしい限りです。この3年間のイタリアでの生活は、帰る場所の大切さを感じる時でもあったと思います。
でも、ローマでも帰る場所が出来ました。カトリックローマ日本人会です。留学してきた人たちや、ローマに住む日本人カトリック信者の月に一度の日曜日の集まり。そう、一時的ではなく、ローマを帰る場所とした人たちがいたわけです。日本人会を通して、終の棲家を外国にと定めた時の気持ちと苦労が分かるようになりました。でも、それ以上に、今ここに、イタリア人との間に、家族や友人という帰る場所があり、迎えてくれる人が、迎える人がいる。素晴らしいことだと思います。
司祭は家族を持たないと言いました。でも、本当は家族を持っています。教会という家族を。カテケジスにおいても、とても重要なこととして、小教区が大きな一つの家族にならなければと言われています。一人ひとりの帰る場所、無条件で迎えられる場所、癒され、出かけていく拠点となるところ。神学的には教会はキリストの身体、共同体となっているとはいえ、実際に、なかなか家族になれていない、帰る場所になれていない現実。特にその凝縮とも言えるのが日曜日のミサなのですが、はたして「ミサに行く」けど「ミサに帰る」という気持ちになれていない。もったいない話だと思います。教会が一人ひとりの居場所となっていくこと、これが特に現代の日本において大切な鍵だと思います。
ローマでの生活で、私にとって帰るべき場所の一つがこの日本人会でした。月に一度とは言え、帰る場所。日本語でミサをして、茶話会をして。ただそれだけかも知れません。でも、イエス様がいて、皆さんがいて、そこで交わり、癒され、新たに出発。本当に助けていただきました。
日本に戻って、これからどうなるのかまったく分かりません。でも、一つ学んだこと、「子どもからお年寄りまで、特に若者たちを無条件で、暖かく迎えること、信頼していつも共に歩むこと」を是非実践しながら、この帰るべき場所作り、家族作りにいそしみたいと思います。3年間支えてもらい続けた自分です。今度は支えることが出来れば。でもきっと支えてもらうことも必要。与え、与えられて歩んでいきたいと思います。離れても、帰る場所を与えてくださった方々に、ローマ日本人会の皆さんのために、祈りで支えていけたらと思います。感謝のうちに・・・。 - 家族の絆、親の愛
-
シスターテレジア古木涼子
 帰10日間の巡礼に参加した時、参加者の中に足の不自由な方がいた。杖をつきながら、一生懸命歩いておられる姿に感心した。いつもニコニコと微笑んでおられ、とてもいい家庭で大切に育てられたのだろうと想像した。ところが、少しずつ驚かされる事実が見えてきた。親に虐待されていたということ。両親を恨んでいたということ。巡礼中にクリスマスのお祝いがあり、「いのち」を歌った。その女性は、「その歌、実は聞いたことがあったの。教会で何度か歌われたんだけど、私、そのたびに、「聞きたくないっ!」って耳をふさいでたの。でも、もう平気。これからはちゃんと聴く。それはね、あなたが作った曲だから。」
帰10日間の巡礼に参加した時、参加者の中に足の不自由な方がいた。杖をつきながら、一生懸命歩いておられる姿に感心した。いつもニコニコと微笑んでおられ、とてもいい家庭で大切に育てられたのだろうと想像した。ところが、少しずつ驚かされる事実が見えてきた。親に虐待されていたということ。両親を恨んでいたということ。巡礼中にクリスマスのお祝いがあり、「いのち」を歌った。その女性は、「その歌、実は聞いたことがあったの。教会で何度か歌われたんだけど、私、そのたびに、「聞きたくないっ!」って耳をふさいでたの。でも、もう平気。これからはちゃんと聴く。それはね、あなたが作った曲だから。」
「実は、この曲を聞いて親から受けた傷を思い出して、かえってつらい気持ちになる人もいるのではないかという心配もあったの。でも、女子少年院で歌った時、受刑者の女の子達が号泣したんだって、、、」と言うと、その女性は「当たり前だよ。そういうところにいる子達が一番、愛されていることを感じるんだから。だって、私の息子、刑務所にいるから、わかるの。」一瞬耳を疑ってしまったが、ニコニコしながら話している姿は、まるで息子さんが刑務所に入ってそのことに気付いてくれたことを喜んでいるようだった。その温かい眼差しに、世間体を気にせず、息子のことだけを想い続ける親の一途な愛を感じた。
ある受刑者の言葉と重なる。「皮肉な話ですが、自分がこんな立場になって初めて親、家族の愛を真剣に考えるようになったのです。こんな犯罪を犯した自分を見捨てずに面会や裁判にまできていただき、そして、今も私が更生して社会に復帰することを疑いもなく待っていてくれている家族の姿を見るたびに、胸が熱くなるのです。」
平成7年の地下鉄サリン事件でサリン製造などに関与したとして、殺人容疑などで逮捕されたオウム真理教元幹部、菊池直子容疑者の両親が発表したコメントに娘への言葉があった。「直子、生きていてくれて、本当にありがとう。」「あなたに会いたい気持ちで一杯です。」社会を全部敵に回してでも、批判の嵐を受けようとも、どうしても伝えたかった言葉だったのだろう。子供への親の愛を誰が阻むことができるだろうか。子供が何をしても、どんな人間であるかにかかわらず、親は無条件に子供を想う。生きている意味がある。そんな親の願いだから。同じように、親が何をしても、どんな人間であるかにかかわらず、子は無条件に親を想う。これは紛れもない事実だ。
シスターテレジア古木涼子(イエスのカリタス修道女会会員)
会の聖歌隊スモールクワイアの3枚目のCD「かけがえのないいのち」に収録されている「いのち」の作詞・作曲者 - 親が子に遺せるもの
-
安武 信吾
 朝の食卓
朝の食卓
午前6時すぎ、小学4年生の娘・はな(9歳)が削るカツオ節の音が台所で響く。前夜から水に浸けていた昆布を沸騰直前に取り出し、削ったカツオ節を鍋に入れる。ワカメを洗い、手のひらの上の豆腐にそーっと包丁を落とす。
「パパ〜。もうすぐ出来るよ。テーブルにご飯とお箸を用意しておいてね」
みそ汁が出来上がった。定番のおかずはこれに納豆と塩麹入りの卵焼き。料理の所用時間は約20分。この数年で、手際も段取りも随分よくなった。
「パパ、きょうのみそ汁の味はどう?」「うん、カツオ出汁がよく効いていてうまいよ。はなちゃん、上手になったね」。はなが満足そうに微笑んだ。
娘は最強のサポーター
2008年7月、妻の千恵が8年間の闘病の末、33歳の生涯を閉じた。最初は乳がん。その後、肺、肝臓、骨に転移した。はなは、がんが肺に再発する直前に産まれた。最初の抗がん剤治療中、主治医からは「出産はあきらめたほうがいい」と指摘されていた。ぼくたちにとって、子を授かったのは奇跡のような出来事だった。
「出産すると、がんの再発リスクが高くなる」。そう聞いていた千恵は、出産を迷った時期もあった。だが、のちにブログにこう書いた。「娘は私にとって最強のサポーター。娘を産んで本当によかった。私が生まれてきた意味はこれだったのかな」。はなのために、食の現状を学び、手料理を作り、生活習慣を見直した。暮らしを改めることは、自分のため、家族のためでもある。再発を繰り返しても、過去を悔やまず、前を見据え、はなの存在と成長を自身の生きる力に変えた。
5歳の誕生日に
千恵は息をひきとる5カ月前、はなを台所に立たせた。5歳の誕生日から、みそ汁の作り方を教えた。なぜ、いくつもの料理の中で最初に「みそ汁」を選んだのだろうか。その理由を千恵に聞いたことがある。
「みそ汁の生きた菌と栄養満点のだし汁が、はなの体温を上げ、病気になりにくい体をつくってくれる。基本の食は、ご飯と具沢山のみそ汁と納豆がいい。みそ汁さえ作ることができれば、いつ一人暮らしを始めても大丈夫だよね」
朝ご飯は食べない。甘いジュースやスナック菓子を食事代わりにする。そんな一人暮らしの大学生が多い、との調査結果をある本で読んだ。千恵は、必要なときは抗がん剤も使ったが、病気予防やがん治療のベースは食と生活の改善であると信じていた。それをないがしろにしては、先進的な西洋医学の治療をやっても意味がないと考えていた。どんなに勉強ができても、台所に立った経験がなく、大人になって過去の食の積み重ねが原因で重い病気になっては何にもならない。食の問題は「今」ではなく「未来」なのだから。
そして、もうひとつの理由を付け加えた。「家族全員で、娘と一緒に作った朝食を並べた食卓を囲む。食べ物に手を合わせ、笑顔で『いただきます』を言う。これって、とても幸せなことじゃない? そんな環境で育った子は、きっと、豊かな人生が送れるはず。でも、今の世の中は、そんな当たり前のことが難しくなってしまったよね」。
親が子に遺せるもの
はなは千恵が亡き後、毎朝早起きして、ぼくのためにみそ汁を作ってくれる。テレビ局の取材で、はなは、こんなことを聞かれたことがある。「はなちゃんはどうして毎朝、みそ汁を作るの?」。はなは迷わず即答した。
「パパがほめてくれるから。パパが笑うと食卓が、ぱーっと明るくなって、よし、またがんばるぞっていう気持ちになるんだよ」
千恵は、自分がいなくなった後の父と娘だけの食卓の風景も考えていたのかもしれない。小学校の教師でもあった千恵は、子どもをほめてあげることの大切さを知っていた。ほめてあげれば、子どもが「自分は必要とされている。価値のある存在」と実感し、自分のことを大切に思えるようになる。そんな子どもは他人のことも思いやることができる。
ある日、はなが千恵と交わした最後の約束を、ぼくにそーっと教えてくれた。「ママはね、はなにこう言ったんだよ。自分の身の回りのことは自分ですること。人の悪口を言わないこと。やさしい女の子になってね、って」。2人の約束と、千恵が娘にみそ汁作りを教えた意味が、ぼくの心の中で重なり合った。プロフィール 安武信吾
福岡県宮若市出身。大学卒業後、西日本新聞社に入社。現在、企画事業局ソーシャル事業部で地域創造プロジェクト「NEWS cafe」を担当。がんで亡くなった奥さんと、娘のはなちゃんとの絆を描いた「はなちゃんのみそ汁」の著者。「はなちゃんのみそ汁」はベストセラーとなり、今年の24時間テレビでも取り上げられた。 - 薬物依存を乗り越えて
-
渡辺 肇
私は板橋区で生まれ、幼い頃に家族で西東京市に移り住み、思春期をそこで過ごした。父は出版社で編集の仕事をしており、仕事熱心だった。そのせいか、子育てや家事のほとんどは母に任せられていたのではないかと思う。しかし、小児喘息もあった小さい私を自然に触れさせようと、両親はよく山や海に連れて行ってくれた。両親からの愛情はたっぷりと注がれていると感じていたが、妹とひと回り離れていたということもあってか、母親は特に私にいろいろな期待をかけていたのかもしれない。小さい時からピアノや習い事をし、小学生になる頃は付きっきりの母のもとでドリルの勉強を初めた。ピアノは練習が厳しく、上手く弾けずに母に怒られるのが怖かった。また家の中では夫婦喧嘩もよくあり、母のヒステリックな声を聞くと、もしかしたら両親は離婚することになるのではないかと不安な気持ちにもなった。おそらく無意識的に両親の間で良い子を演じ、いつも親の顔色を伺うように育っていたのかもしれない。
父は仕事熱心ではあったが、私が小学生の頃はリトルリーグの監督もしており、近所のベトレヘム学園という施設に一緒に連れて行ってくれた。私はキャッチボールなどをしていたが、その施設にはシスターもいた。その頃、両親はベトレヘム学園から里子を引き取ったので、自分の家ではその子たちたちと一緒に生活をはじめ、休みの日にはリトルリーグの練習に明け暮れた。遠い夏の日の記憶だ。
私たちのチームのレベルは高く強豪ではあったが、私はリトルを卒業した後、中学受験に落ちて西東京の中学に入った。リトル出身組は甲子園まで行く組と不良グループを形成する組とに別れた。私は後者の不良グループへの仲間入りをし、家庭では親に反発した。里子たちに対しては自分の親の愛情、特に母親の愛情が自分に向かなくなることを恐れて不安になり、意地の悪いことをした。リトル出身組は都内でも有名な不良グループで、当時は校内暴力も吹き荒れ、中3の時には10対10の中学生同士の白昼の決闘で新聞沙汰になる始末だった。みな野球で鍛えていたので体格もよく運動神経もずば抜けていて、近隣の中学や都内でもケンカばかりで有名になってしまった。
私は度々家出をした。あんな家!と…。そうした時に薬物に出会い、その時はなんとか高校に進学しおさまったが、再び大麻などに出会い、それをゲートドラッグにどんどんエスカレートしていき、ハードドラッグへと移行した。コカインや咳止め薬、覚せい剤・・・。気づいた時には、それなしではいられない心と体になっていた。心の中のあらゆる痛みと寂しさは薬によって一瞬にして消えてなくなるが、人生のすべてが薬物に支配されていてはどうすることもできなかった。そうこうしている時、母親が、当時生まれたばかりのダルクを探し出してくれた。そこでロイ(Roy)神父と出会った。最初の出会いの際、「よく来たね。良かったら一緒にやめませんか?」と言ってくださったことを今でも覚えている。ある医師は「ダルクへ行け!君の病気はたとえ病院に入院したとしても治してやることはできない。ダルクへ行きなさい」と言って追い返した。しかし今となってはその彼も武蔵野ダルクや仲間のことで相談にのってくださったり、支援してくださったりしている。
 ダルクと関わるようになって、時には失敗もしたが、いろいろなことを学びながら奇跡のように薬物への依存は止まった。しかし神は、安らぎの戻った私たち家族の上にまた試練を与えられた。アメリカに留学をしていた私に、母が癌になったという連絡が入ったのだ。しかももって三カ月。当時NYに在住し、以前ダルクとマック時代に施設でお世話になったシスターに連絡したところ、「帰ってあげなさい」と言われ、帰国を決意した。信濃町の病院に通い神に奇跡を祈りながら看病した。(神様なぜこのような試練を与えるのですか? 母は何も悪いことをしていない。どうしてですか?)とすべてのこと腹立たしくなりながらも、50歳になったばかりの母の寝顔を見ては、(死ぬはずがない、神様が奇跡を起こしてくれるはずだ)と神を信じ、(神様、治して下さい!)と祈った。病室にロイ神父とブラザーが祈りに来てくださった、母の閉じていた目が一瞬開き、微笑んだ。
ダルクと関わるようになって、時には失敗もしたが、いろいろなことを学びながら奇跡のように薬物への依存は止まった。しかし神は、安らぎの戻った私たち家族の上にまた試練を与えられた。アメリカに留学をしていた私に、母が癌になったという連絡が入ったのだ。しかももって三カ月。当時NYに在住し、以前ダルクとマック時代に施設でお世話になったシスターに連絡したところ、「帰ってあげなさい」と言われ、帰国を決意した。信濃町の病院に通い神に奇跡を祈りながら看病した。(神様なぜこのような試練を与えるのですか? 母は何も悪いことをしていない。どうしてですか?)とすべてのこと腹立たしくなりながらも、50歳になったばかりの母の寝顔を見ては、(死ぬはずがない、神様が奇跡を起こしてくれるはずだ)と神を信じ、(神様、治して下さい!)と祈った。病室にロイ神父とブラザーが祈りに来てくださった、母の閉じていた目が一瞬開き、微笑んだ。
 翌朝、母は息をひきとった。私は神に(なぜだ!なぜだ!)と怒り、事実をどうしても受け入れられなかった。マリア堂の中で泣きながら棺の横にいると、エルナンデス修道士が「お母様はマリア様の所に行ったよ」と肩を叩いて下さり、恩人の医師も来て「祈ろうよ」と言って下さった。
翌朝、母は息をひきとった。私は神に(なぜだ!なぜだ!)と怒り、事実をどうしても受け入れられなかった。マリア堂の中で泣きながら棺の横にいると、エルナンデス修道士が「お母様はマリア様の所に行ったよ」と肩を叩いて下さり、恩人の医師も来て「祈ろうよ」と言って下さった。
次の試練は葬式から半年ちょっと経った頃だった。父が再婚をすると言い出した。父から相手の女性を紹介された時、私は「祝福したいがもう少し待ってほしい。」と伝えた。しかし父は再婚し、(ふざけやがって!)と怒りを抑えられず、酒に煽り、クスリの世界にスリップした。街で母に似た容姿の女性を見かけるとハッとし、母が歩いているかのように見えたりした。
紆余曲折の人生だったが、幸いに命を落とさずに再び今日を生きていること、また、神から与えられた命に感謝できるようになり、再び歩き出すことができた。デーケン神父様の講話を聞きに行き、死についてよく考えるようにもなった。昨年の東日本大震災でも本当に多くのことを考えさせられた。そして自分に与えられた役割についてもいろいろと考えた。今でも苦しみや寂しさの中にいる人たちは沢山いる。アルコールや薬物の問題に苦しむ人や家族も相談に来ている。ネットでクスリを手に入れる危険性を子供たち、青少年たち伝えていきたい。神から与えられた自分の役割を、今も苦しさと寂しさの中にいる人たちの中で果たしていきたい。
人はいつどこでどうなるかわからないし、死は神の領域だろう。だから、神が与えて下さる今日を大切に生きていきたい。そう思いながら武蔵野の緑を目にすると、生かされている今に感謝することができる。良いことも辛い経験もすべて、振り返るってみると神の計画の中にあることがよくわかる。神様、今日、あなたの意志が働かれますように。あなたの意志に従い今日一日を歩むことができますように。与えられている命を感謝します。苦しさと寂しさの中にいる人たちにその喜びを伝えていくことができますように。神に感謝! プロフィール 渡辺 肇(カトリック高幡教会所属)
プロフィール 渡辺 肇(カトリック高幡教会所属)
1966年東京都板橋区生まれ。西東京市出身 Arts S of NY 卒。1986年DARCでリハビリ後、マックダルク後援会の職員として働く。
2006年三河ダルク代表 豊橋刑務所薬物離脱教育に入る。
2008年帰京後、社会人として会社勤務2010年モンドセレクション撮影カメラマンとしてパリ、ベルギーに出張。3.11経験後、退社。2014年より武蔵野ダルクの活動をスタートする。秋元病院アルコール薬物デイケアプログラム担当。10月には豊島区役所アルコール薬物福祉研究会で講演を予定している。 - ある受刑者との出会い
-
小林 誠
 私は刑務所勤務の内科医で、病気の受刑者の診療をしています。刑務所に勤務する前、受刑者は体格が良く、恐い顔つきで全身に入墨がある、というようなイメージを持っていました。実際に診療した受刑者達は、高齢者や他人とうまくコミュニケーションが取れない人、軽度な知的障害を持った人など弱々しい人がたくさんいました。
私は刑務所勤務の内科医で、病気の受刑者の診療をしています。刑務所に勤務する前、受刑者は体格が良く、恐い顔つきで全身に入墨がある、というようなイメージを持っていました。実際に診療した受刑者達は、高齢者や他人とうまくコミュニケーションが取れない人、軽度な知的障害を持った人など弱々しい人がたくさんいました。
刑務所で受刑者が診察を受ける時、受刑者は診察室の入り口で称呼番号という受刑者一人一人に与えられる3桁の番号と名前を言ってから、診察室に入ってきます。田中さん(仮名)という50代の男性受刑者がいます。彼は知的障害があり、自分の称呼番号がどうしても覚えられません。いつも診察室の入り口で「えーと、えーと」と言って、困ったような顔をします。警備に付いている刑務官がイライラしているのが分かります。私は思わず「123番だよ。」と彼の番号を言ってしまい、彼もほっとしたように「123番田中、入ります。」と言って診察室に入って来ます。
彼は手術ができない肝臓癌ですが、癌の病巣にいく血管を詰まらせ、癌を小さくする治療が可能で、刑務所に入る前に何度かその治療を受けてきました。私は今回もその治療を受けることを勧めました。しかし「その治療は辛くはないけど、治療を受けて生きて刑務所を出ても、社会で生きていく自信がないから、もう治療は受けなくていい。」と言います。日を改めて合計3回治療を勧めました。田中さんに治療を勧めている時、私の心には、Sr.古木涼子が作曲・作詞した「いのち」という曲の「生きて!生きて!生きて欲しい」というフレーズが繰り返し流れてきて、祈るような気持ちで彼の返事を待ちました。しかし、結局彼は3回とも治療を拒否しました。田中さんの家族に、病気の説明をするため連絡を取ったのですが、家族は「今まで彼には散々迷惑を掛けられてきました。もう連絡をしないで下さい。」と言ってきました。彼は刑務所に入る前から家族とも疎遠だったようです。
その治療をしなければ、彼は数ヶ月から1年程で亡くなるでしょう。患者がどのような医療を受けるかを自分で判断すること自体は尊重されるべきだと思います。しかし「社会で生きていく自信がないから」という理由から、治療を受けないということは、大変悲しいことです。彼にとってこの世はとても生きづらい場所だったのでしょう。せめて最期には「この世も悪くなかったなあ」と思えるように、私は彼と向き合っていきたいと思います。プロフィール
小林 誠 医師・カトリック信者
数年前刑務所内で行われたクリスマスコンサートで、スモールクワイアと出会った。 - 貧しいことが貧しいと言える社会へ
-
岩田 鐵夫
 「貧しい人に福音を」と聖書に書かれています。しかし豊かと言われてきた日本での生活保護の大きな問題は、生活保護基準以下で生活し、本来なら生活保護を受けられる人の8割から9割の人が受けられていないことなのです。
「貧しい人に福音を」と聖書に書かれています。しかし豊かと言われてきた日本での生活保護の大きな問題は、生活保護基準以下で生活し、本来なら生活保護を受けられる人の8割から9割の人が受けられていないことなのです。
生活保護利用者が過去最高になったと言われていますが人口に対する利用率は2.4%から1.6%に減少していますし、先進諸外国と比べても極めて低い数字にとどまっています。また不正受給がクローズアップされていますが、実際は保護費全体の0.3%程度なのです。
「生活保護法」は昭和25年に制定され「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされています。法の理念としては、保護ではなく保障が優先されているのですから、最も重要なのは「最低限度の生活を保障する」ことで、名前(呼称)を「生活保障法」に変更すべきだと思います。この名前(呼称)の弊害として挙げられるのは、今まで生活保護申請の受付窓口である福祉事務所が、生活保護の受給を窓口という「水際」で阻止し、違法に保護申請の受け取りを拒否した通称「窓際作戦」によって申請の権利を阻害しているケースが挙げられます。これは自己責任論だけで片づけてしまいがちな生活困窮者に対する私たちの差別的な意識の反映だと思います。私も生活保護を申請に行く生活困窮者にしばしば付きい添い同行しますが、まさに生活保護申請の現場は修羅場であり、闘いの場と感じています。
25年前、札幌市白石区で福祉事務所に相談したにも関わらず「若いから働け」「離婚した夫に扶養を頼め」と言われ、生活保護を受けられなかった母子家庭の母親が衰弱、餓死し、その3人の子どもが取り残されたという悲惨な事件がありました。このことがまったく反省されずに今年の1月同じ札幌市白石区で42歳と40歳の姉妹の病死、凍死事件が発生しました。姉は福祉事務所を3回訪ねましたが、生活保護の申請用紙さえ渡されませんでした。生活保護が必要な人に対して申請用紙すら渡さないという対応は、政府や厚生労働省が生活保護をできるだけ抑制したいという政策の表れで、申請ではなく相談という形で追い返す「水際作戦」がいまだに面々と悪しき伝統として続いている現実があります。
適正な生活保護行政が行なわれていれば「尊いいのち」を失うことがなかったであろうことと思うと、とても無念でなりません。なぜ救えた「いのち」が救えなかったのか。また東京都立川市では2月に45歳の母親と4歳の男児が死後1~2ケ月で発見されました。母親がくも膜下出血した後に知的障害を持つ子供がオートロックの部屋に取り残され餓死したものと思われています。また3月に同じ立川市で95歳の母親と63歳の娘が亡くなっているのが死後1ケ月で発見されました。認知症の母親を介護する娘が急死し、母親も衰弱死したものと思われています。行政の福祉のケースワークの低下、見守りサービス・老介護のサポート不足が指摘されています。
最近は夫婦・親子など複数家族が餓死する例が多く見られます。生活保護を受けることは決して恥ずかしいことでも、隠さなければならないことでもないと思います。生活保護をもっと受けやすくし、生活保護漏れを無くしていくことが大切だと思います。
このような時に女性週刊誌の報道から端を発し、国会にまで取り上げられたタレントの生活保護「扶養義務」の問題で、「不正受給をしているのではないか」といわゆる生活保護バッシングが巻き起こっています。テレビや週刊誌などで騒がれる中、受給者が「生活保護を受けている自分が悪いのか」と精神的に追い詰められたり、「結婚した娘からの援助をもらわなければならないのか」と申請をためらい、萎縮している人たちが増えています。
このように生活保護バッシングが行われていることで、ますます生活困窮者がSOSを出しにくい社会になっていくことや、さらに自分はSOSを出していいんだろうかなど自己価値を低くしていく人が増えていくことを危惧しています。
私たちが、いのちを守る社会、支え合う社会を目指すのであれば、生活保護バッシングに惑わされることなく、間違った情報や様々な偏見を乗り越えて正しい知識を身につけ、助けを必要とする人が「困った」「お金がない」ということが言える、そしてすぐに相談できる環境を作りたいものです。そのためにも日本の貧困率(2009年度16%)が年々悪化している現状や適正な生活保護行政を行うよう国の施策にも声をあげていきましょう。プロフィール 岩田 鐵夫・カトリック麹町教会信徒
- 社会福祉士・精神保健福祉士
- 日本CLCメンバー 鎌倉黙想の家の運営チーム世話人
- 聖イグナチオいのちを守るプロジェクト(自死の問題に取り組む)
- 聖イグナチオ生活相談室(生活困窮者の相談)
- 聖イグナチオ・カレーの会(ホームレスのためのカレーの炊き出し・毎週月曜)
- IMA緊急シェルター(ホームレス・難民・DV被害者などの緊急な居場所提供)
- きらきら星ネット(震災と原発によって東京に避難されている家族のサポート)
- フェイス トゥ フェイス(被災地岩手県釜石へのボランティア派遣)
- 社会福祉士・精神保健福祉士
- きずな -お互いが信頼で結ばれること-
-
萩原 栄三郎

「きずな」という言葉は、2011年3月11日の東日本大震災・大津波や福島第一原発事故の後によく耳にするようになりました。大きな災害を経験した私たちは目覚め、人間の本来の姿を見つめ直す貴重な体験をすることになりました。この体験には多くの方の大きな犠牲が伴っていることをわたしたちは片時の忘れてはなりません。経済第一、効率化、合理化の掛け声の騒音にかき消されていた心の声が、あの甚大な災害後の沈黙と静けさの中で大きな響きとなって、私たちの心の耳に聞こえるようになったのです。私たち人間は、機械ではない。皆が互いに支え、また支えられて生きている存在であることを思い出しました。これまで自分たちが大切にしてきたものが一瞬にして失われた時、私たちは五感では捉えることのできない尊いものが存在することを再び認めることができるようになりました。「きずな」という言葉は、私たちが生活する中で、他の人との複雑な繋がりを大切にしなければならないことを表現したすばらしい言葉だと思います。
この「きずな」を深め、大切にするには三つの大切な柱があると私は思います。その柱は信・望・愛です。その第一の柱である「信」とは、お互いが信頼で結ばれることです。ところで、この信頼心を築く作業を誰から始めたらよいのでしょうか。もし私が[あの人が私を信じるなら私も信じてやろう]と考えるとしたら、いつまでたっても信頼関係を築くことはできないと思います。私は自分が人を信じて仕事をしているつもりでした。つまり、信じた「つもり」だったのです。信じるとは「信じたつもり」ではいけない、信じるとは疑いを自分の心の中からすべて取り除くことにあることを、小学4年生のE君との関わりの中で教えられました。その時の私の体験をお話ししたいと思います。
E君は私たちの施設で生活していましたが、E君は他の子どもたちと一緒になって、毎日のように問題行動を起こし、しばしば地域の人たちから苦情が寄せられ、又警察にも補導されることもありました。私たち施設職員は繰り返される問題行動の後始末に追われ困っていました。職員たちはE君とその仲間に対して、「あなたたちはこれまでに何回『もうこれから絶対しません』と約束したのね?」と手の指を折り曲げながら問題行動を起こすたびに彼らを諭していました。
ところがある日、E君が園長室に突然入ってきて、入るなり大きな声で「僕はこれから一生ウソをついて生きて行きます」と宣言したのです。これまでのE君の生活状態を知っているわたしは何事が起ったのかと思いました。それでE君に尋ねました。「どうしたのか」と。するとE君は「先生が自分を信じなかった」と興奮しながら答えました。職員たちからE君の行動について、「本当のことを云わない、約束は守らない毎日」と聞かされていた私も、実をいうとE君のことを信じていませんでした。ですから、先生がE君を信じられなかったことも理解できました。E君に「先生は何を君に言ったのか」と尋ねると、E君は「ぼくは、今日外に出て行っていないのに、君も行ったんだろう」と云われたことに憤慨していたのです。E君は仲間のリーダー格で、いつも先頭に立って問題行動を起こしていましたので、職員はそのような言いぐさをしたのだと思います。しかし、E君は先生のことばにプライドを傷つけられたのです。そこで私はE君に「それでは君は今日から嘘をつかないんだね? そしたら園長は今日から君の云っていることを信じる」と云って、E君に「嘘をつかないように」と念を押しました。するとE君は「いいよ」と云って退室していきました。
しかし、E君は次の日もこれまで同様、仲間と一緒になって問題行動を起こしました。ところが、その時からE君の行動に変化したことが一つありました。それは問題行動を起こした後、E君は自分たちがやってきた問題行動の一部始終を報告するようになったことです。それまで職員はあたかも刑事のようにE君たちの行動を調べ上げるのに時間を費やしていましたが、その日から刑事役の仕事をしなくてもよくなったのです。もちろんE君らの問題行動はしばらく続いたのですが、ある日からE君は問題行動を全く起こさなくなりました。そして仲間にも問題行動を起こさないように注意する場面を見かけるようになりました。E君とのこのようなかかわりを通して、私は子どもたちと信頼関係を築くために何が必要で、大切なことかをE君から教えてもらいました。
(1)人を信じること。しかも疑うことなく、とことん信じること。
(2)相手の失敗を過去に遡って数え上げないこと
(3)相手の失敗を他の失敗とからめて責めたてたり解決しようとしないこと。
(4)人間は誰でも弱さをもっていることを認め、私自身もその一人であることを素直に認めること
(5)人間は弱さゆえに約束を破ることがあり、最初から嘘をつこうとしているのでなく,
約束する時は絶対守るという決意をもっていると信じること。しかし、人間は時間が過ぎ、場所が変われば自分の弱さに負けてしまう。そして自分の失敗を素直に認めることのできない弱さ、プライドを守ろうとすることから言い訳が多くなり、ついついそれが嘘になってしまうこと。
(6)私という人間が変わって、相手を心から信じられる人間、そして相手が心から私に信頼をおける人間に私がなることが一番大切なこと。
(7)どの人も自分を信じてくれる人が、少なくとも一人はいなければ生きていけないこと。
私は、E君との関わりを通して、自分の秤の小ささや、自分のものの見方の歪みをはっきりと見せつけられました。大切なことは、子どもたちを変えることにあくせくするのではなく、私自身が変わるために本気で取り組めばよいことに気づかされました。 プロフィール
プロフィール
萩原 栄三郎
コンベンツアル聖フランシスコ会司祭
児童養護施設 聖母の騎士園園長
カトリック小長井教会主任司祭 - 手繰るきずな
-
伊藤惠子
 病院に勤めていると、多忙さを言い訳にして仕事の周辺には目を向けないようにする自分がいる。それでも、時に「生老病死」の実相に圧倒されることがある。人々の病いの物語を縦軸として、ひとの感覚の妙や感情の奥深さに触れる機会だと思う。
病院に勤めていると、多忙さを言い訳にして仕事の周辺には目を向けないようにする自分がいる。それでも、時に「生老病死」の実相に圧倒されることがある。人々の病いの物語を縦軸として、ひとの感覚の妙や感情の奥深さに触れる機会だと思う。
離れて暮らす家族の場合は、普段行き来がなくても誰かが病いでピンチになれば押っ取り刀で駆け付けてくれる。恐縮する本人が「長く生き延びると家族に迷惑がかかるから、いっそ早くお迎えが…」とつい弱音を吐き、家族から一蹴される。「早く治療してまた元気になってよ」と。 「回復を願う」家族がいるという安心は、思わぬ大病で揺らいでいる者にとって、どれだけの希望をもたらすか想像に難くない。
家族の一員が精神障害を抱えていれば、時に邪推や妄想のために小さな親切心も曲解されて不和を助長しかねない。家族として十分な支援を表明したくても、病人の余裕のないこころを尊重すれば、静かな援助の手で充分である。声高に語らず、まるで祈りのような支援だ。 家族なればこその、信頼できる「きずな」だと納得する。
Aさんは幼い頃両親が離婚、兄弟が父方母方にそれぞれ引き取られ、離れて暮らした。就学前のAさんは、自分を残して家を出ていった母を怨みながら成長した。耳の手当てが遅れ、難聴で少し会話が苦手であったが、黙々と職人の技を磨き 全国を転々として暮らした。大病を得て残された時間が大分厳しいと思われた頃、ご家族から申し入れがあった。「絶縁状態だった実母がAさんに会いたがっている」。
Aさんはどう感じるのだろうか。感動の再会という美談に、私達皆が浮足立ってないだろうか。予想される事態をいくつか伝え、「ご家族でよく話し合ってほしい。複雑な思いが本人にはあるようだから」と最後に結んだ。 結局、兄弟たちの決断もあり、実に50余年ぶりの再会が実現した。高齢の母が病身の息子を見舞うというのはそれだけでも心に負荷がかかるだろう。母子はただ手を握り合ったまま、涙と無言のひと時だったと後にうかがった。 母もAさんも互いのわだかまりが融けたのであれば、それは'無縁'に見えていたけれど「家族のきずな」の仕業だったのかも知れない。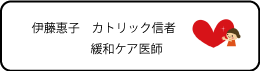
- 避難家族の絆を支える
-
信木 美穂
 東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故によって東京に避難してきた子どもたちやその家族をサポートする活動に携わってもうすぐ2年が過ぎようとしています。原発事故によって、福島県から全国に避難している人びとは、いまだ5万人を超えています。原子力発電所の事故は、多くの人びとを故郷から去らせ、家族を離ればなれにしました。家族のささやかな日常を引き裂き、家族が共に過ごせるはずだったかけがえのない時間を奪いました。
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故によって東京に避難してきた子どもたちやその家族をサポートする活動に携わってもうすぐ2年が過ぎようとしています。原発事故によって、福島県から全国に避難している人びとは、いまだ5万人を超えています。原子力発電所の事故は、多くの人びとを故郷から去らせ、家族を離ればなれにしました。家族のささやかな日常を引き裂き、家族が共に過ごせるはずだったかけがえのない時間を奪いました。
今、原発事故の影響で全国に避難している多くの家族は、離ればなれになった家族との絆をなんとか保ちながらも、計り知れない苦しみを背負っています。家族の絆は、簡単に断ち切られるものではありませんが、長く続く別居生活、避難生活にのしかかる経済的な負担、母親の育児の負担、家族が離ればなれに暮らすことによって生じるコミュニケーション不足、避難生活についての夫婦間の考え方の相違、父親と暮らせないことで募る子どもたちのストレスなどが避難世帯を苦しめ、その絆を少しずつ傷つけていきます。
震災時には、まだお母さんのおなかにいた男の子。臨月に近かったその女性は、近所の人たちに少しずつガソリンを分けてもらい、夫の運転する車で真夜中に東京に避難しました。東京で出産した後、生まれたばかりの赤ちゃんと二人、母子状態で暮らす生活が避難所で始まりました。その男の子は、現在1歳9ヶ月になります。福島に帰省したときにおじいちゃんと電車を見るのが日課になり、東京に戻ってきてからも電車を見るのが大好きです。避難者交流サロンに来ると、スタッフに「電車を見たい」と訴えます。そして、本当のおじいちゃんと年齢が似ているスタッフの男性を「じいじ、じいじ」とうれしそうに呼び、一緒に散歩にでかけていきます。その孫の成長をそばで見ることができない本当のおじいちゃん。そして誰よりも、その子の父親が抱える、自分の子どもが日々愛らしく成長していく姿をそばで見ることができないという苦しみ―。
二人の乳幼児を抱えて避難し、母子家庭状態を切り盛りする若いお母さんは、福島に残っている家族との軋轢に悩みます。「もうそろそろ帰ってきてもいいんじゃないの」「放射能の危険もほとんどない、って言ってるよ」「線量もだいぶおさまったよ」「孫の顔を見られないのは寂しい。帰ってきなさい」?そんな家族や親類の言葉が、女性の心を傷つけます。福島の放射能汚染被害。食べ物、生活の場所、子どもが遊ぶ場所。その影響が計り知れない今、幼い子どもの健康被害に不安を感じる女性は、福島に戻る決断はできないのです。その上、購入したばかりの自宅は多額のローンが残り、風評被害のために売却できる見込みがありません。家をどうするのか。福島に残した家族をどうするのか。離れて暮らす夫とのこれからの生活をどうするのか。尽きない悩み。将来への不安。狭い避難先の住宅で、子どもと自分だけで過ぎて行く日々。若いお母さんたちは、育児と生活に疲れ、精神的にも追いつめられていきます。
「どうして私のパパは一緒に住んでいないの?どうしてパパと時々しか会えないの?」。震災と原発事故の直後に東京に避難した時には、2歳だった女の子。まだおしゃべりが上手にできない時期で、パパと離ればなれになった理由と意味がわかりませんでした。今、幼稚園に通うようになり、おしゃべりがとても上手になりました。その幼い子が大人たちに向かって問います。「どうして私はパパと一緒にいられないの?」「パパにね、時々しか会えないの」「◯◯ちゃんのパパはお家にいるけど、私のパパはいないの」。幼い子どもの言葉が、両親の心に突き刺さります。愛する子どもたちと離れて暮らす父親は、どれほど子どもたちに会いたいでしょうか。どれほど子どもたちを毎日抱きしめてあげたいでしょうか。
これからいつまで避難生活が続くのか。まったく見通しが立たない中で私たちに求められているのは、原発事故によって全国に避難している家族たちとともに歩んでいくことではないでしょうか。若いお母さんたち、幼い子どもたちを、家族のように思い手を差し伸べること。また、避難せずに福島に暮らす子どもたちやその家族のことにも思いを馳せること。原発事故によって、放射能汚染被害によって、日本中のとてつもなく多くの人が傷ついている今、私たちはともに手をたずさえその傷を少しでも癒しあい、多くの人が余儀なくされている長い避難生活という苦しみをともに経験し、放射能汚染被害の中にあっても希望を失わずに前にすすんでいきたいと思います。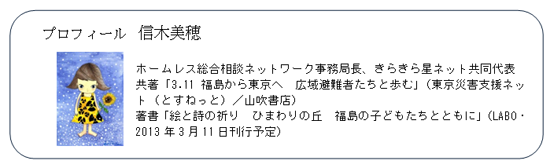
- 祈り ―家庭のきずな―
-
シスターテオドラ朴 正心
 長い間、私の記憶に残っている一つの美しい話があります。
長い間、私の記憶に残っている一つの美しい話があります。
本修道会のシスターたちが運営している幼稚園であった出来事です。シスターたちは毎日、幼稚園に来る園児たちを迎えながら、また幼稚園にいろいろな行事がある時、そして病気の子供たちのためにいつも子供たちと共に祈りをしていました。ですからカトリック信者ではない園児たちも自然に祈りを学び、お祈りする習慣が身につきました。嬉しいことや大変なことがあった時、子供たちは、まず祈りをするのです。
ある日、その幼稚園に通っている一人の子供が病気になって病院に入院しましたが、その子の両親は高熱に苦しんでいる子供に何をしてあげればいいかわからなくて、「何か食べたいものがある? 欲しいものはない? お母さんとお父さんに望んでいるものは何?」…と尋ねました。
その時、子供が両親に「私が病気になって苦しんでいるのに、お母さんとお父さんはどうして私のために祈ってくれないの?幼稚園ではすぐに祈ってくれるのに…。お母さん、お父さん、私のために祈ってください。」と言ったそうです。高熱に苦しんでいる息子の願いに、両親はすごく慌てました。
その子の両親は信仰をもってなかったので、息子のために祈ることを考えもしなかったし、祈りを願われても、どのようにいのればいいか分かりませんでした。そこでその子の両親は幼稚園に電話をしてシスターに助けを求めました。シスターたちはすぐにお見舞いに行き、その子のために祈ると子供は安心しました。
その様子を見ていた両親は大きく感動し、その子が退院すると幼稚園にお礼に来ました。まず、自分たちの息子のために祈ってくださったシスターたちに感謝し、自分たちをキリスト教に導いてくれるよう願いました。そしてシスターたちはその子の両親を教会に案内し、彼らは息子と共に教会で洗礼を受け、神の子になったという話です。 - 沖縄から「家庭のきずな」を考える
-
山田圭吾

2011年3月11日の東日本大震災以来、「絆(きずな)」という言葉がいたるところで見聞きされた。
それまでもあった言葉なのに、特別なことが起こった時等に殊更に取り上げられることは、ままあることであるし、ある程度の年月が経てば忘れられてしまう、あるいは意識されなくなってしまうことも経験することである。
それまで「絆」がなかったわけではなく、あまり意識されていなかっただけではないだろうかとも思うのだが、しかしまた、それを強調しなければいけないほど、弱くなっていたのかとも思われるのだ。
日本のカトリック教会では、1987年に第1回福音宣教推進全国会議(NICE-1)「開かれた教会づくり」を、そして1993年に第2回福音宣教推進全国会議(NICE-2)「家庭の現実から福音宣教のあり方を探る」を開催した。
それまでのカトリック教会の中で、どちらかというと教会は閉鎖的ではないのか等の反省から、教会をもっと開かれた存在にしないといけないとの声があったことから「開かれた教会づくり」が掲げられ、さらには「家庭」の現実を見つめることによって、信仰の振り返りをし、宣教に結び付けようということだったのだろう。
しかし、上記の「絆」にしても、「開かれた教会づくり」や「家庭の現実から福音宣教のあり方を探る」にしても、不断の努力なしには、風化し、忘れられていくものではないだろうか。家庭(夫婦、親子、兄弟姉妹)や、親戚関係、地域との関わり、それぞれの所属する様々な団体においても、「絆」というものはほっといても「ある」ものではなく、何もしないで「培われる」ものでもないだろうし、また強められるものでもないだろう。現に、このナイスについてさえも今、語られることはほとんど見られない。
ところで、4月28日は、1952年のこの日、日本が独立し、主権を回復したとされているが、その実、沖縄(県)、奄美群島、小笠原諸島が切り離されていたことが、多くの日本人から忘れられているような風潮である。そのような中で、今年は日本の「主権回復の日」として式典を開催するという。
このことについて、沖縄はこの日を「屈辱の日」と呼び、奄美では「痛恨の日」と呼んでいることが、日本政府の方々には、そして多くの日本人には思いが至らないのだろうか。
日本(国)の都合により、勝手に日本の領土に組み入れたり、あるいは人身御供のように他国に献上して切り離したりしてきた。まるで、家族の生活を守るために、口減らしとして我が子を売ってしまった時代のようだが、それでも、そのことを祝う家族があるだろうか。そして、この沖縄を差別する構造は今でも続いているのだ。
日本国土のわずか0.6%の沖縄は、その土地の10%が米軍基地であるが、米軍による日常的な事件・事故に関しても日本はほとんど無視してきた。その沖縄では、軍用地をめぐり家族同士での諍いもあったりして、家族や地域共同体の「絆」の崩壊も懸念されている。また、名護市辺野古に新しい基地を建設しようとする日本政府によって、「アメ(金銭等)とムチ(強制的な嫌がらせ等)」で家族や地域共同体が分断されようとしているのだ。このような流れに抗うためには、それぞれの「絆」を固め、強めていくことが求められている。
この日本という国の中でも、国民同士の「絆」を大切にし、そのことによって、他国との「絆」をも深めていくことが、「平和」を創り出していくことに繋がっていくことと思う。そのためには、より一層の「祈りと行動」が求められるだろう。
山田圭吾(泡瀬教会/那覇教区) - ぼくは見ていたよ
-
あるインドのサレジオ会員の書いた詩
ぼくは見ていたよ
ぼくは見ていたよ。
母さんはぼくが初めて描いた絵を冷蔵庫に貼ってくれた。
それで、すぐに次の絵を描きたくなった。
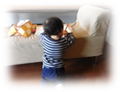
ぼくは見ていたよ。
母さんはおなかをすかせた野良猫に食べ物をやった。
動物に優しくするのはよいことだと学んだ。

ぼくは見ていたよ。
母さんはぼくの好きなお菓子を作ってくれた。
小さなことが、人生では特別なことになると知った。

ぼくは見ていたよ。
母さんは料理を作って、病気の友人を見舞った。
ぼくたちは皆、互いに助け合わなければいけないのだと知った。

ぼくは見ていたよ。
母さんは家のこと、家に住むみんなのことを世話していた。
ぼくたちは、いただいているものを世話するものだと悟った。
 ぼくは見ていたよ。
ぼくは見ていたよ。
母さんは、気分がよくないときでもすべきことを果たしていた。
ぼくも大きくなったら責任があるのだとわかった。
 ぼくは見ていたよ。
ぼくは見ていたよ。
母さんの目から涙がこぼれるのを見た。
時には痛みがある、その時、泣いていいのだとわかった。
 ぼくは見て
ぼくは見て
人生の教えのほとんどを学んだ。
大きくなったら、よい人間、周りの人を思いやる
人間にならなければならないことを学んだ。 - こころのふるさと
-
シスター テレジア浜辺直子
 緊急一時保護をお願いしたいです」と児童相談所より電話が入る度に身が引き締まります。ほとんどが虐待通告などで、行き詰った家庭の中で傷ついた子どもの保護です。相談所の先生方に付き添われて玄関に訪れる子どもの表情は、どこか遠くを見つめたような、きょとんとした感じです。
緊急一時保護をお願いしたいです」と児童相談所より電話が入る度に身が引き締まります。ほとんどが虐待通告などで、行き詰った家庭の中で傷ついた子どもの保護です。相談所の先生方に付き添われて玄関に訪れる子どもの表情は、どこか遠くを見つめたような、きょとんとした感じです。
日本の文部省唱歌に「ふるさと」という歌があります。その2番の歌詞には特に心温まるものがあります。
いかにいます(どうしていらっしゃるだろうか)父母
つつがなしや(無事だろうか) 友がき(友達)
風に雨に つけても 思いいずる(思い出す)ふるさと
ふるさとは、あたたかい場所、帰りたい場所、生きる力を汲み取ることのできる思い出の場でした。ストレスによる経済的困窮、離婚・再婚等が社会を脅かしている昨今、親の不安や生きづらさが即、子どもたちへの虐待などに繋がり、子どもたちは怯えて震える心を全身でギリギリ抱え込んでいることもあります。
日々こうした子供たちと養護施設の中で関わらせていただいていますが、何人か親の所在が分からない子どもがいます。今は親との距離をおかなければいけない状況もありますが、子どもたちは「お母さんに会いたい」「お父さんに会いたい」とあたかいふるさとを求め続けます。私たち養護施設で関わらせていただく者は、子どもたちがいつの日か、自分たちで親に会い、自立して自分で生きる力を養うために、家庭で親がするようにとはいきませんが、関わった分の温もりが、いずれ心のふるさととなれるよう、小さな愛の援助を、手と眼差しや微笑みを通して日々分かち合っています。
息詰まることも多いですが、それでもなお神様への心の携帯電話を鳴りっぱなしにしながら、信仰の世界での大きな家庭のきずなを思い、祈り続けます。神様がふるさと。限りない信頼と希望のうちに、人間の世界で何があろうと受け取っていただける場所、帰ることのできる最終的な心の家なのですから。 - 長女の結婚
-
小池喜子
 2013年7月14日の日曜日に、長女が結婚式を挙げた。
2013年7月14日の日曜日に、長女が結婚式を挙げた。
娘が、生まれ育った静岡を出てから9年目になる。福井県で大学生活を送り、そのまま向こうで仕事についている。人柄のよい福井の青年と、長くお付き合いしているのは承知していた。静岡にも、時々一緒に来ているので、娘が結婚したいと伝えて来た時は、驚くこともなく、良かったと思った。
娘の仕事が大変忙しいので、簡単で良いから教会で式を挙げるように話すと、生まれた時から通ってきた静岡の八幡教会で挙式したいと答える。 八幡教会ならば、母親の私がすべて準備してあげられる。けれどこちらは良いが、新郎のご家族にとっては大変なことではないかと思い、福井へ出向いてあちらのご両親と話をした。 挙式は静岡で、披露宴は福井でと、快く賛成してくださった。
それからは安心して挙式の準備をした。教会の仲間と友人が寄り添うように協力してくれて、相談しながらスムーズに準備ができた。挙式当日、新郎のご親戚が20人以上も、遠方から来てくださった。キリスト教や教会を知らない方たちが、娘の育った宗教と文化を、無条件で受け入れて、初めて教会を訪れた。
教会の仲間はお手伝いをしてくれながら、静岡の親族も、そして日ごろご無沙汰している友人たちも喜んで集まってくれた。新郎新婦が入堂する。お聖堂に、振袖と羽織袴のふたり。違和感はなく自然。新郎が呉服屋の息子さんだから。最初の聖歌は“いつくしみふかき”。心を合わせてみんな大きな声で歌ってくれた。たくさんの仲間たちの温かい心が、二人を祝福して、一つになってお聖堂に響き渡る。深くて力強いその響きを聴きながら、感動で胸が熱くなった。 一人一人が、そしていくつもの小さな家族が、若い二人の出発を喜び、祈りあう大きな家族になった。
退堂の時、紙ふぶきを浴びて歩く二人のうれしそうな顔!!
この日、娘は親から離れて、独立し、新しい出発をした。同時に、娘を育ててきた私たちに、そして二女にとっても、温かい新しい家族が増えたことを実感した。それは思わず微笑みがこぼれるほどうれしい感覚である。 新郎を育ててきた家族の深い愛情は、これからは娘もいっしょに包んで支えてくれることだろう。わたしたちも二人を見守り、応援し続ける。
増えた家族の、優しい、愛情のきずなを感じて、幸せな気持ちを、あれからずっと味わっている。プロフィール
小池喜子
静岡八幡聖母幼稚園卒、静岡雙葉中学校高等学校卒
臨床心理学修士 幼い子どものためのセラピスト
カウンセラー 虐待防止活動と被害者支援に取り組む。 - 結婚
-
シスター松本豊子
- 「神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。
- 男と女に創造された。神は彼らを祝福していわれた。
- 「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。」
- (創世記1章27~28節)
 このように人間は父と子と聖霊という愛の交わりである神に似せて造られたものであり、愛に生きることが人間の使命であるといえます。神は最初男だけをおつくりになりますが、「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」(創世記2章18節)と女をおつくりになりました。愛である神に象って造られた人間はある時期がくると愛する人と出会い結婚し、自分たちが育った家族を離れ新しい家族を築き始めます。しかし結婚は決して自分たちの意志だけによるものではなく、神様からの尊い恵みなのです。婚姻と夫婦愛は子供を産み育てることに向けられていますが、夫婦はお互いの一致を深める努力をし、その絆はけっして解消されてはならないものです。何故ならその絆は神様によって結ばれたものなのですから。
このように人間は父と子と聖霊という愛の交わりである神に似せて造られたものであり、愛に生きることが人間の使命であるといえます。神は最初男だけをおつくりになりますが、「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」(創世記2章18節)と女をおつくりになりました。愛である神に象って造られた人間はある時期がくると愛する人と出会い結婚し、自分たちが育った家族を離れ新しい家族を築き始めます。しかし結婚は決して自分たちの意志だけによるものではなく、神様からの尊い恵みなのです。婚姻と夫婦愛は子供を産み育てることに向けられていますが、夫婦はお互いの一致を深める努力をし、その絆はけっして解消されてはならないものです。何故ならその絆は神様によって結ばれたものなのですから。
しかし結婚生活が甘く楽しいことばかりではありません。私たち一人一人はそれぞれ違うユニークな人間ですからたとえ愛し合う者同士でもぶつかり合うことがあるのは当然です。ぶつかり合いの原因は様々だと思います。自分たちだけでは解決できない問題もあるかもしれません。大切なことは夫婦の互いのコミュニケーションではないでしょうか。(この人に何を言っても埒があかない、馬の耳に念仏のようなものだ)と、言いたいことも言わず、お互いに問題をうやむやにしておくと、小さなことも大きな問題に発展しかねません。
対話には先ずお互いの違いを受け入れ相手を尊重する姿勢が大切です。先入観を持たず相手の言うことにじっと耳を傾けましょう。夫婦と言えども伴侶の全てを知っているわけではないと思います。忍耐強く相手を理解したいとの気持ちで聞くことによって、相手の中に、そして自分自身にも新しい何かを発見するかもしれません。
日本人は思っていることを口にすることがあまり上手ではないかもしれません。特にそれが身内へのほめ言葉だと躊躇しがちです。まして人前で身内をほめるようなことはあまりないのではないかと思います。ある時フィリピン人の知人宅に招待されたことがあります。その時、奥様のお料理がとても美味しかったので、「美味しいですね」というとご主人がすかさず「本当に彼女は料理がうまいんですよ。いつもありがとうね。」と客の前でも自分の奥さんをほめ感謝のことばを口にしました。そして奥さんも旦那さんからの感謝のことばを素直に受け「ありがとう」と返しました。傍からも見ても仲睦ましいと感じていたご夫婦、そして温かいご家族のその秘訣を、その時知ることができたように思いました。決して当たり前ということはなく、私たちは誰かによって支えられ生かされているのですから、感謝の気持ちを忘れずそれを言葉で伝えることはとても大切だと思います。
そして何よりも夫婦はお互いのために祈ることを大切にして欲しいと思います。
私たちにお互いの欠点を受け入れる忍耐をお与えください。
人生の様々な困難を乗り越えていくために
助け合う心を互いの誤解によって壊さないでください。
平和と喜びのうちに生きることができる恵みをお与えください。
怒るにおそく、すぐに赦すことのできる心をお与えください。
あなたの愛で私たちの子供愛し、隣人を助け、
共同体と社会に奉仕していくことができますように。
私と夫(妻)が真の愛を互いに理解することができますように。
私たちが互いに信頼し合うことができますように。
私たちが互いに平和と調和のうちに生きることができますように。
いつもお互いの弱さを受け入れ、互いの強さによって成長できますように。
アーメン。 - 新しい出逢い ~里親制度~
-
シスターマリア・ローザ谷口幸代

・・・ねぇ~ ○○ちゃんのママ、来る?・・・
・・・○○ちゃんも、ママ、行きた~い・・・
子ども達は、自分の気持ちを伝えられる年齢になってくると、里親交流や保護者の面会がある子どもの様子を感じ、いろんな会話が飛び出してきます。
私たちの施設は、さまざまな家庭の事情により家庭で暮らすことのできない乳幼児をお預かりしています。一般的に、このお子さん達を、家庭に代わって公的に養育する仕組みを「社会的養護」といいます。その中でも児童福祉施設ではなく、もっと家庭的な環境で子ども達を養育する「家庭的養護」の中に里親制度があります。里親委託の中にも養育家庭・専門養育家庭・親族里親・養子縁組里親があります。里親とは、あたたかい家庭のぬくもりを求めているお子さんを、自分の家に迎え入れて、愛情とまごころをもって養育して下さる方のことです。昨年から私どもの施設では、里親支援専門相談員という専門職を配置しました。年間数件ですが、児童相談所・関係機関と連携し、お子さんが新しい出逢いの中で、家族と生活を始めていくお手伝いをさせて頂くとともに、里親制度の啓発普及にも努めています。またご縁があり、民間団体の趣旨“子どものいのち、人生、未来のため、また子どもの幸せのために”という思いを受けて、特別養子縁組のご家庭に、育児支援という形で数日間関わらせていただいています。 抱っこの仕方、ミルクの作り方や授乳の仕方、オムツ交換にお風呂の入れ方、またお帰りになってから、早目に近くの小児科を捜すこと等など、また赤ちゃんの思いや表情、様子なども話していきます。いかに愛情を持って、子どもの思いを汲み取って支援していくかが大切です。これは、里親さんに限らす、乳幼児と関わる私たちのプロ意識にも繋がってきます。
今回は、その関わりの中で感じることをお話しさせて頂きます。
関わる特別養子縁組のお子さんは、生後数日から数カ月の乳児です。子育て研修の依頼があると、「産みの親」と「育ての親」が来寮され、初めてこの時に会われます。もちろん種々の情報などは全くなく、お子さんを受け入れる覚悟でお見えになります。赤ちゃんは、大事に大切にされながら、「産みの親」の腕から「育ての親」の腕に託されます。この時、両方の親の目には必ず、子どもの幸せを願う涙があります。「産みの親」は、言葉には出来ないいろんな思いの中で、子どもの将来を考えて特別養子縁組を選択されるのだと思います。新しい出逢い、新しい家族の始まりです。「育ての親」はお子さんを迎え入れた時から、産んでくれた親の存在を伝え続けるそうです。(テリング)。
このテリング(Tell+ing)は、子どもに「産みの親」が大切な温かい存在である事を伝え続けていくこと、また子どもの思いに耳を傾けていくこと等、「育て親」と子どもとの信頼関係に基づくもので、生き方を尊重する連続的な関わりだと言います。お話によると物心つくときには、お母さんが2人いる・・・という感覚を持つとのことです。いろんな思いや葛藤があると思います。しかしその中で、母の存在やいのちは、大事に引き継がれていると感じます。
(・・・そうかー、私たちも産みの親と、私たちを育てて下さる天におられる親・神さまと2人・・・)
妙に納得します。
また東京都では、「里親」の中でも、養子縁組を目的とせず、子どもを育てている家庭を、養育家庭(ほっとファミリー)と呼び、一人でも多くの子ども達がほっとファミリーのもとで育つよう制度周知に努めています。「里親」「里子」にとって、悩みや苦労、葛藤、また楽しさや喜びなど、沢山あると思います。子どもの幸せのために取り組むいろんな活動に関わらせて頂く機会がある中で、神さまの計らいの中で、安らぎと大きな実りになるよう祈りたいと思います。子どもの笑顔の魔法にかけられて、じつは、いつも元気をもらっているのは、私たち大人です。
子ども達の幸せな笑顔があふれますように・・・。
新しい出逢い、神さまのめぐり逢わせが、素敵な出逢いとなりますように・・・。
未来ある子ども達が、愛されて、元気に成長できますように・・・。
(・・・信仰の目では、産みの親は、神さまで、育ての親は、両親・・・)
子育ては、神さまから地上の親への里親委託で、神さまと親との共同養育と言えるかもしれませんね。10月11月は里親月間です。近くの関係機関でも、様々な取り組みが行われますので、子ども達の幸せに寄り添う、小さな出逢いの輪を広げてみませんか。 - ドン・ボスコの親心
-
浦田慎二郎
 司牧の現場で子供たちと接していて常に感じることは、当たり前のことですが、「家庭の大切さ」です。家庭で子供たちがどのように愛され、教育されているかによって、こちらが伝えようとしていることの伝わり方が全く異なるのです。ですから、教会などにおいても、子供たちに対してだけではなく、ご両親たちに対してこちらがどのようなものを提供できているかが問われていると感じています。
司牧の現場で子供たちと接していて常に感じることは、当たり前のことですが、「家庭の大切さ」です。家庭で子供たちがどのように愛され、教育されているかによって、こちらが伝えようとしていることの伝わり方が全く異なるのです。ですから、教会などにおいても、子供たちに対してだけではなく、ご両親たちに対してこちらがどのようなものを提供できているかが問われていると感じています。
しかしまた同時に、今の社会ではそのような家庭の素晴らしさを直接味わうことがなかなかできない子供たちも増えてきています。そのような子供たちに対して、私たちができることは何でしょうか。
「青少年の友」と言われるドン・ボスコは、まさにそのような子供たちを相手にしました。彼らに対して、ドン・ボスコは「親代わり」になったのです。町に一人で働きに出かけ、道で暮らしているような子供たちを集めて、彼らに住む場所と、パンと、勉学と、仕事と、そして何よりも愛を与えました。ですから、ドン・ボスコは「父・ドン・ボスコ」とも言われるのです。
ドン・ボスコのその父の愛情は、しかし、ただ単に地上の親代わりをするだけではありませんでした。その先をも見せていたのです。ドン・ボスコは自分を捨てて彼らに愛を示すことによって、実は、「天の父」である神様の愛を若者たちに体験させていたのです。若者たちは理屈ではなく、体験として、ドン・ボスコを通して「自分たちを愛してくれている父が天にいる」ということを知りました。
このように考えるとき、私たち教育者の責任の重みがより深く感じられます。私たちが接する子供たちが私たちを通じて、神様の「親の愛」を感じることができますように。プロフィール
浦田慎二郎(うらた・しんじろう)
サレジオ会司祭。教皇庁立サレジオ大学神学部霊性神学博士課程修了、 神学博士。専門はドン・ボスコ研究。現在、カトリック下井草教会に隣接するSITEC(サイテック:研修施設)館長。著書:「フランシスコ・サレジオと共に歩む 神への道」 監修:『ドン・ボスコのことば100』(ドン・ボスコ社) - 絆
-

相良 敦子
もう20年くらい前、フランスに半年ほど滞在したときのことである。ある小学生に、「兄弟は何人ですか?」と訊ねたら、「今日ですか、週末ですか、バカンス中ですか?」と逆に私に訊ねた。「今日であれば、私一人、週末にはパパの前の子どもが二人来るから、三人兄弟、バカンスは、ママの前の子どもが二人来るから五人になる」というのである。当時のフランスは、結婚・離婚を数回繰り返す人が多く、その度に生まれた子どもたちが、様々な形で親と生活する。そのような生き方を「ステップ家族」とか「モザイク家族」といっていた。その頃から、フランスの結婚の形態は多様に変化していき、公的な書類に「結婚」以外に「同棲」という形態も認められるようになっていった。結婚した夫婦が一つの家庭を生涯守り抜くという形態は昔のことになってしまったようだ。
こうなってくると、「家庭のきずな」という場合、必ずしも「血縁によるつながり」を基盤として語ることができない。「血縁のつながり」イコール「家庭のきずな」ではない、別の「きずな」の要素があるようだ。 そういえば、東日本大震災の時、「家も家族も地域も仕事も何もかも流され…きずなだけが残った」と、誰かが語っているのをテレビで見た。
私たちが生きるこの世界では、全てが取り去られることはあり得る。昨今は、想定外の大地震、大事故、大きな台風や高潮などに見舞われ、家族も財産も何もかもを奪われた人々の痛ましい姿が度々報道される。このような出来事は、必ず起こるのだと聖書は既に予告している。次のようなイエスの言葉がある。「ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。『あなたがたはこれらの物に見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。・・・あなたがたは親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。・・・』」(ルカ21の5~16)。この箇所から、親、兄弟、親族という血縁のきずなも崩れ去り、奪い取られる性質のものだということがわかる。
実際、かって経験しなかった社会現象や自然現象にさらされる現代の家庭の現実を見ていると、血縁のつながりを基盤にして「家庭のきずな」を語るのは難しい。「大津波で家も家族も何もかもなくなり、きずなだけが残った」と言った人が教えてくれたことは、「愛」だけが「きずな」だという真理であったと思う。その「愛」は、強者と弱者、持てる者と持たない者、優越者と劣者、との間に成り立つ関係ではなく、双方が尊重し合い、双方が必要とし合い、双方から支え合う間柄に息づくほのぼのとしたぬくもりと生きる力である。それは、聖父と聖子と聖霊の三位一体の関係とその内面に息づく愛と生命の投映である。
全てを失い、全てを明け渡し、「委ねます」と神様に向かって叫ぶ、そこからしか真の「家庭のきずな」は生まれないのであろう。プロフィール
相良敦子(さがら あつこ)
長崎純心大学大学院教授、 エリザベト音楽大学客員教授、日本モンテッソーリ協会(学会)理事、東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンターをはじめ全国各地のモンテッソーリ教師養成コースで講義を担当。 - サレジオ家族のきずなに結ばれて
-
シスター井口みはる(イエスのカリタス修道女会会員)
私は2年間、サレジアンシスターズの霊性コースで霊性を学ぶため、サレジアンシスターズのシスター方と過ごしました。そのコースで学ぶ40名ほどのシスターと10名のスタッフのシスターが生活する大きな共同体でした。その霊性コースはサレジアンシスターズのためのものですが、私の所属する修道会、イエスのカリタス修道女会は、サレジアンファミリーという30の修道会、活動グループで組織されている団体の一つということで、特別に一緒に学ばせていただきました。
 そのコースのまとめとして昨年、つまり2013年の夏に、ドン・ボスコゆかりの地を歩きながら、彼が実際に行なったこと、彼が始めたオラトリオの初期の話などを聴き、それについて考え、分かち合いをする。というとても贅沢で貴重な体験をさせていただきました。
そのコースのまとめとして昨年、つまり2013年の夏に、ドン・ボスコゆかりの地を歩きながら、彼が実際に行なったこと、彼が始めたオラトリオの初期の話などを聴き、それについて考え、分かち合いをする。というとても贅沢で貴重な体験をさせていただきました。
そこで体験したことの中の一つで、ドン・ボスコが建てたトリノの扶助者聖母の大聖堂に入ったときのことです。ドン・ボスコについても学び、彼の存在が少し近くなったので、この有名な大聖堂に入ったらきっと心が震えるほど感動するだろうと期待していました。ところが感動しなかったわけではないですが、感動するはずだった大聖堂であるにもかかわらず、毎日自分がそうしているかのように祈り始め、そしてドン・ボスコに向かって話しをしていたのです。自分がしていることがあまりにも日常的すぎたのでそのために驚きました。あとからの話しと、分かち合いで、この大聖堂、初めての人はとても感動するようなのですが、2回目、3回目あるいはそれ以上と回を重ねた人は、大聖堂に入った時感動するとういうよりも、“よく帰ってきたね”という、包み込むような暖かさを感じるそうなのです。この大聖堂に入るのが初めてではなかった私も例外ではなく、大聖堂に入ってすぐに「ただいま!!」とドン・ボスコに挨拶をしていたのです。ドン・ボスコが偉大な聖人ということだけではなく、イエスのカリタス修道女会のメンバーの一人である私にとっても父であり、その父を中心としたドン・ボスコの家族つまり、サレジアンファミリーという家族の一員であるということをあらためて自覚しました。
実は一年前の2012年の夏に、似たような体験をしていました。
1年間ともに学んだ仲間、サレジアンのシスター20名と一緒にサレジアンシスターズの発祥の地モルネーゼに行ったときのことです。到着したその日、私は聖女マリア・ドメニカ・マザレロの生誕の家に行きました。そこに入った瞬間、自分が家族の一員であるということをはっきり感じたのです。聖女マリア・ドメニカ・マザレロは私たちの修道会にとっては、実のところドン・ボスコほどの存在感はなく、どちらかというと馴染みの薄い聖人ですが、サレジアンシスターズにとっては、修道会の協働創立者であり、初代総長であり、模範であり、何よりも母であり、ドン・ボスコと並んで大切な聖人です。どうやら意識する、しないに関わらず、ともに学び、生活しているうちに、彼女たちが大切にしているものが、私にとっても大切なものになってきたのでしょう。それはファミリーとしてのきずながあればこそ感じることができたものではないでしょうか。確かに、以前はサレジアンファミリーといっても、いくつかの共通点はあるものの、実際はあまりファミリーという意識は持っていませんでした。ともに生活し、学び多くのことを共有することによって、私はサレジアンファミリーというきずなを感じることができるようになったのだと思います。そのためにわたしにはこの2年間があったのだと思っています。
きずなとは『断ち切りがたい人と人との結びつき』です。家庭のきずなは神様が結んでくださったものです。その結びつきは断ち切ることはできません。その断ち切りがたい結びつきに気づいていないことが多いのではないでしょうか。その結びつきに気づくために、共有する時間、あるいは共通のもの(者、物)はとても大切だと思います。
新しい一年、家庭の中で、あるいは共同体の中で共有する時間やものを増やすことによって、さらにきずなを深めることが出来たらと思います。
 イエスのカリタス修道女会
イエスのカリタス修道女会